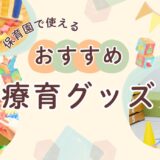”境界性パーソナリティ障害”という言葉を聞いたことはありますか?境界性パーソナリティ障害とは、青年期までに発症することが多い精神疾患の1つです。英語を略してBPD(Borderline Personality Disorder)とも呼ばれています。この疾患の国内有病率は約0.5~1%と言われていますが、境界性パーソナリティ障害について詳しく知っているという人は少ないのではないでしょうか?この記事では、境界性パーソナリティ障害の症状や発症する原因、治療法など、境界性パーソナリティ障害について詳しく解説します。正しい知識を持つことで理解が深まり、当事者や周囲の人が適切に向き合うための手がかりとなるでしょう。
境界性パーソナリティ障害とは?
感情や人間関係が極端に不安定になる疾患

境界性パーソナリティ障害とは、感情や人間関係が極端に不安定になる疾患です。人間は、陽気や明るい、神経質、几帳面、怒りっぽいなどその人それぞれの性格を持っています。しかし、境界性パーソナリティ障害の人は、それらの1部分が極端に偏ってしまいます。極端な感情の偏りは社会生活を送るうえで、自分や他人を苦しませてしまうことがあります。また、そうした社会生活での困難からうつ病や不安障害、薬物依存など、他の精神疾患を同時に発症することも少なくありません。
境界性パーソナリティ障害の症状は?
自己像があいまいで頻繁に変化

境界性パーソナリティ障害の人に見られる症状1つ目は、自己像があいまいで頻繁に変化することです。自分自身に対する評価や感覚が一貫せず、目標や価値観、意見、趣味などがその時々で大きく変わってしまいます。また、自分に対するイメージがあいまいなため、他人からの影響も受けやすいでしょう。自己像の不安定さにより、「自分が自分でない」「生きている実感がない」と空虚感や孤独感を感じることもあります。さらに、他人からは「意見がコロコロと変わる」「一貫性がない」と捉えられ、周囲から距離を置かれてしまうこともあるようです。
感情のコントロールが困難
2つ目は、感情のコントロールが困難なことです。境界性パーソナリティ障害の人は、怒りや不安、悲しみなどの感情が急激に沸き上がり、本人の意思で抑えることが難しい傾向にあります。例えば、情緒が0か100かのように極端になりやすいため、些細なことで気分が一気に落ち込んだり怒りに満ちたりすることもあるでしょう。感情をコントロールできないことにより、自傷や浪費などの衝動的な行動につながりやすく、対人関係も不安定になりがちです。
見捨てられることへの強い不安

3つ目は、見捨てられることへの強い不安を感じることです。境界性パーソナリティ障害の人は、周囲の人から離れられたり拒絶されたりすることに対して、極端に過敏で強い恐怖を感じてしまいます。実際に見捨てられるという状況だけでなく、返信が遅かったり声のトーンが普段と違ったりなどの些細なことにも激しい不安を感じてしまうようです。大きな不安から、相手を責め立てたり突然関係を断ってしまったりすることもあるでしょう。
人間関係が極端で不安定

4つ目は、人間関係が極端で不安定になりやすいことです。境界性パーソナリティ障害の人は、物事を白か黒か、0か100かという二分的な思考をしがちです。対人関係においても一度味方だと感じた相手を理想化して強く信頼します。一方で、自分の意見や要求に沿わない場面が出てくると、すぐに相手を全否定してしまうことがありますよ。こうした思考パターンは人間関係の安定を妨げ、健全で持続的なコミュニケーションを築くことを難しくしてしまうでしょう。
自傷的な行動
5つ目は、自傷的な行動です。境界性パーソナリティ障害の人は、他者に見捨てられることへの極端な不安や孤独感から、自分には価値がないと感じやすくなります。その結果、感情のつらさを和らげたり相手に助けを求めたりする手段として、自傷的な行動を繰り返してしまうことがあるでしょう。具体的な自傷的な行動として多く見られるのは、自殺未遂やリストカットなどの直接的な行為です。また、自傷的な行動は薬物やアルコールの乱用、万引き、過食、過度な買い物などの依存行動にまで及ぶことがあり、その範囲は非常に多岐にわたります。
境界性パーソナリティ障害を発症する原因は?
生まれつきの性格

境界性パーソナリティ障害を発症する原因は、まだ明確には解明されていません。しかし、環境的な要因や身体的な要因などがいくつか考えられています。まず始めに考えられる原因は、生まれつきの性格です。幼い頃から不安を感じやすく、人との関わりに強い緊張を覚える子どもは、集団生活の中で孤立したり、人間関係にうまく適応できなかったりすることがあります。そうした経験が積み重なることで、自分に自信を持てず、他者への依存や見捨てられることへの過敏さが強まってしまうでしょう。それはやがて境界性パーソナリティ障害発症の土台となってしまいます。
遺伝子
身体的な要因の1つとして、遺伝子による発症も考えられています。脳の感情を司る部分(扁桃体や前頭前野)の機能や構造に違いが見られ、感情の反応が過敏で制御しづらいことがあります。また、両親が境界性パーソナリティ障害に罹患していると、子どもがこの病気にかかる確率が約5倍になるという説もあるそうです。ただし、親の情緒不安定さそのものが単純に遺伝する可能性は低いと言われていますよ。遺伝的要因だけでなく環境要因との複合的な影響が大きいと考えられています。
幼少期の養育環境

境界性パーソナリティ障害の発症要因として最も大きいとされているのは、幼少期の養育環境です。境界性パーソナリティ障害の人は、幼少期に虐待を受けていたり保護者との離別や死別を経験していたりするケースが多くあります。このような状況では、大人との健全な愛着関係を築くことができません。幼少期に、安心して自己形成ができる安定した愛着関係を築くことができなかったため、感情の調整が難しく、自己像や対人関係が不安定になると考えられています。一方で、子どもが成長した後も母親離れや子ども離れができない共依存状態でも、境界性パーソナリティ障害を引き起こしやすいと言われています。
心的外傷体験

また、心的外傷体験も境界性パーソナリティ障害発症の要因となります。心的外傷体験とは、事故や災害、虐待など生命や心の安全が脅かされる強いストレス体験のことを指します。前述した幼少期に受けた虐待や保護者との離別以外にも、友人関係のもつれや恋人からのDVなども発症の要因になり得ますよ。これらの体験がフラッシュバックすることで強いストレスがかかり、境界性パーソナリティ障害の発症につながっていると考えられています。
境界性パーソナリティ障害のチェックリスト
5項目以上当てはまると可能性あり
境界性パーソナリティ障害の診断を行う際は、さまざまな心理テストや患者と近しい人への問診などが行われます。代表的な診断基準として、以下のようなものがあげられます。
- 見捨てられる体験を避けようと懸命に努力する
- 不安定で激しい人間関係が特徴。他者に対する評価が理想化と過小評価の間で激しく変化する
- 常に自己像(アイデンティティ)や自己感覚の不安定さを持っている(同一性障害)
- 衝動的に自分を傷つける可能性のある行動をする(薬物乱用や異常な浪費など)
- 何度も自殺を試みたり、自分の手首を切りつけたりするなどの自傷行為を繰り返す
- 著しく感情が不安定になる
- 慢性的に虚しさや退屈を感じる
- 思い通りにいかない場合などに激しい怒りを感じ、感情のコントロールができなくなる
- 一時的に妄想や重症の解離症状(自分が自分であることの感覚を失った状態。記憶が抜け落ちてしまう、知らぬまに思わぬ行動をしてしまうなど)を生じる
境界性パーソナリティ障害の治療法は?
心理療法

境界性パーソナリティ障害の治療法は、大きく2つに分けられます。1つ目は、心理療法です。境界性パーソナリティ障害の患者に対しては、この心理療法が中心で取り入れられるでしょう。心理療法の具体例としては、以下のようなものがあげられます。
| 心理療法 | 方法・効果など |
|---|---|
| 弁証法的行動療法 | 週1回の個人およびグループセッション。ストレスに対処する、より適切な方法を患者が見つけるのをサポート。とくに、自殺行動の減少、怒りのコントロールに効果的。 |
| システムズトレーニング(STEPPS) | 週1回のグループセッションを20週間行う。自分の感情をコントロールし、否定的な予想の正当化を疑い、自分自身を適切に対処。 |
| メンタライゼーション | 人が自分や他者の心の状態について考え、理解する能力をメンタライゼーションと言う。自分と周りの人の感情や思考などを理解し、それらが自分と他人の行為にどう影響を与えるか、距離を置くかトレーニングする。 |
| 転移焦点化精神療法 | 患者と精神療法家の交流に重点を置く。質問を行い、患者の非現実的な自己像や歪められた思考に対して、どう対処するのかサポート。患者が自分と他者について、安定した現実的な感覚が育める。 |
| スキーマ療法 | 生涯身についた思考、感情、行動、対処法に関する、不適応なパターンを明らかにし、健全なものに置き換える。少なくとも週1~2回、3年間のセッションが必要。 |
| 一般的な精神医学的管理 | 一般医向けにデザインされた療法。患者の自立心を高めるために、人間関係の構築する能力を優先的に治療。 |
参考:『境界性パーソナリティ障害』一般財団法人 日本精神医学研究センター
薬物療法

2つ目は、薬物療法です。心理療法が中心ですが、必要に応じて薬を投与する薬物療法も取り入れられます。薬物療法の具体例としては以下のようなものがあげられます。
| 治療 | 効果 |
|---|---|
| 気分安定薬 | 抑うつ、不安、気分の変動、衝動性の緩和 |
| 非定型(第2世代)抗精神病薬 | 不安、怒り、一過性のストレスに関連した認知の歪みを軽減 |
| 抗うつ薬(SSRI) | 抑うつや不安の緩和 |
参考:『境界性パーソナリティ障害』一般財団法人 日本精神医学研究センター
境界性パーソナリティ障害を抱える人への接し方
ありのままを冷静に受け止める

では、境界性パーソナリティ障害を抱える人に対してどのように接すると良いのでしょうか。1番大切なことは、ありのままを冷静に受け止めることです。ありのままを冷静に受け止めるとは、境界性パーソナリティ障害の人の感情や言動を否定したり無理に変えようとせず、一喜一憂せずに落ち着いて相手を受け止める姿勢を持つことを言います。相手のそのままを尊重することで安心と信頼感を与え、関係の安定化にもつながるでしょう。また、感情的な反応で返すよりも、冷静な対応や一貫性のある接し方が効果的ですよ。
適切な距離をとる

適切な距離を保ちながら関わっていくこともとても重要です。自分の限界や無理のない範囲を守り適切な距離をとることは、双方が疲弊せず安定した関係を続けていくために不可欠なことです。具体的には、頼まれごとや感情的な対応についての境界線(ルール)を設定すると良いでしょう。「夜中の連絡には応じない」「金銭の貸し借りはしない」などです。支える側が無理をしないことで、サポートする人自身の心身の健康や生活が守られ、長期的なサポートがしやすくなるでしょう。
あせらず長い目で見る
治療をあせらずに長い目で見ることも大切。境界性パーソナリティ障害は治療や安定までに長い時間がかかることが多いため、焦って急な改善を求めると本人や周囲の負担が大きくなってしまいます。一気に変化や改善を求めず本人のペースや感情の流れを尊重しながら長期的な視点で支えることで、本人の安心や信頼、症状の改善につながるでしょう。感情の波が激しくなったり衝動的な行動が増える時期があっても、「今はこういう時期なんだ」と冷静に受け止めることが重要です。
専門家に相談する

また、専門家に相談することも欠かせません。困りごとや悩みごと、わからないことが出てきたときは、精神科や心療内科、地域の相談機関などの専門家に無理せず相談しましょう。精神科や心療内科では、専門医が本人の症状や成育歴、家族の状態などをしっかりと問診し、本人に適した治療法を提案してくれます。地域の保健所や行政の福祉窓口では、症状や生活の悩みに専門相談員が対応し、必要に応じて医療機関や自助グループ、訪問看護などにつなげてくれますよ。こうした専門的支援を活用することで、本人や周囲の人が安心感を得て、無理なく長期的にサポートできる環境を整えやすくなるでしょう。
まとめ
本人と周囲が安心できる関わりを目指しましょう

いかがでしたか?今回は、境界性パーソナリティ障害の症状や病気を抱える人への接し方など、境界性パーソナリティ障害について詳しく解説しました。境界性パーソナリティ障害の治療には、周囲のサポートや協力が欠かせません。しかし、接し方を間違えると支える側が大きく疲弊してしまう可能性もあります。境界性パーソナリティ障害についてしっかりと知ることで、本人も周囲の人も安心できる関わりを目指していきましょう。