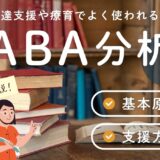皆さんは特別支援学級という言葉を耳にしたことがありますか? 特別支援学級とは、通常の学級とは別に設けられた、療育や個別支援を中心に行うクラスのことです。多くの小学校や中学校に設置されており、子どもは普段の学校生活を送りながら、必要に応じて支援を受けることができますよ。近年は発達障害や学習面のつまずきに対応する場として注目されており、特別支援学級に入るべきか迷う保護者の方も少なくありません。この記事では、特別支援学級の種類や入級までの流れ、判断の基準について分かりやすく解説します。子どもの学びや成長に合った環境を選ぶための参考にしてみてくださいね。
特別支援学級とは?
特別な支援が必要な子どもの学級
特別支援学級とは、通常の学級での学習や生活に困難を感じる子どもに対して、少人数で手厚い支援を行うための学級です。学習の進み方や理解のスピードは一人ひとり違いますが、特別支援学級ではその子どもの特性に合わせて授業内容や進度を工夫します。また、担任や支援員が個別に関わる時間が多く取れるため、安心して学校生活を送れる環境が整えられていますよ。さらに、通常学級と交流する時間も設けられており、集団生活の経験を積みながら社会性を育むことができるでしょう。
療育を通して個々の成長を支える学級

特別支援学級では、単に学習の遅れを補うだけでなく、子どもの発達段階に応じた療育的な支援も重視されています。療育とは、子どもが自分らしく成長していけるように生活面・社会性・感情面をサポートする取り組みのことです。例えば、コミュニケーションの方法を練習したり、身の回りのことを自分でできるように支援したりと、学力以外の面でも成長を促していきますよ。こうした支援を受けることで、子どもは少しずつ自信がついていき、日常生活や将来の社会参加につながる力を育むことができるのです。
特別支援学級の対象となる子どもとは?
対象となる7つの障害に該当する子ども
特別支援学級の対象となるのは、文部科学省が定める7つの障害に該当する子どもです。具体的には以下の障害が挙げられます。
・知的障害
・肢体不自由
・病弱
・弱視
・難聴
・言語障害
・自閉症や情緒障害
これらの障害は子どもによって程度や表れ方が異なるため、一律に同じ支援が行われるわけではありません。その子の得意なことや苦手なことを踏まえ、個別の教育支援計画を立てて学習や生活をサポートします。特別支援学級の対象の子どもたちは、通常学級だけでは学びづらさや生活上の困難を抱えやすいため、特別支援学級という環境が成長の大きな支えとなっています。
特別支援学級の種類は?
知的級

2種類ある特別支援学級の1つが知的級です。知的級は、知的な発達に遅れがある子どもを対象としており、7つの障害の中では特に知的障害や言語障害を持つ子どもが多く通っていますよ。特徴としては、生活面よりも学習面でのつまずきが大きいことです。食事や着替えなど日常生活の基本は自分でできても、通常学級の授業内容を理解し、ついていくことが難しい場合があります。そこで、知的級では少人数の環境で先生が繰り返し丁寧に説明したり、補助教材を活用したりして、子どもが自分のペースで学習を進められるように支援していますよ。
情緒級
もう1つの特別支援学級の種類が情緒級です。情緒級は、知的な遅れはほとんどないものの、コミュニケーションや感情の安定性に課題を抱える子どもを対象としています。自閉症や情緒障害のある子どもが在籍することが多いのが特徴です。学習面では、通常学級と同じ授業を行う場合が多くありますが、子どもによっては自分なりの学習方法を必要としたり、集中を保つための特別な支援を受けることもあります。授業以外では情緒面の安定をサポートし、安心して学校生活を送れるようにすることが重視されていますよ。
特別支援学級を選ぶときの判断基準は?
学習のつまずきの程度を見る

特別支援学級を検討する際には、子どもの学習面でどの程度つまずきがあるのかを確認することが大切です。特に読み書きや計算など基礎的な学習に大きな遅れが見られる場合は、通常学級よりも特別支援学級での学びが適しているケースが多いですよ。また、子どもによっては得意な科目と苦手な科目の差が大きく、部分的なサポートで十分な場合もあります。こうした特性をきちんと見極めることで、その子に合った学習環境を選び、自信を持って学びを積み重ねることができます。
対人関係やコミュニケーションの様子を見る

特別支援学級を検討するときは、子どもが社会的なコミュニケーションをどの程度取れるかも大切な判断基準となります。これは特に情緒級が設置されている学校であてはまるケースですね。例えば、自閉症や言語障害を持つ子どもの場合、通常学級では友達や先生とうまくやり取りができず、学校生活に大きな負担を感じることがあります。家庭の中では問題なく見えても、集団生活の場では問題が出ることも少なくありません。入学後に初めて気づくケースもあるため、普段から子どもの様子を観察し、把握しておくことが大切ですよ。
子どもの情緒や性格の安定性を見る
特別支援学級を検討する際には、子どもの情緒や性格の特徴を考えることも大切です。発達障害の場合、はっきりと診断が出る子もいれば、グレーゾーンとされる子も少なくありません。そのため、障害の有無だけで判断せず、普段の情緒の安定や性格の傾向に目を向けることが重要ですよ。例えば、気持ちが不安定で感情の起伏が大きい場合や、マイペースで人に合わせることが極端に難しい場合には、特別支援学級の方が安心して過ごせることもあります。子どもが自分らしく学校生活を送れるように、特性に合った環境を選ぶことが大切ですよ。
子どもの知的発達の程度を見る
特別支援学級に入るかどうかを判断する際には、子どもの知的発達の程度、つまりIQ値も1つの目安となります。一般的に、IQが70以下の場合は通常学級での学習が難しいとされ、知的級での学びが勧められることがありますよ。一方で、IQが70を超えていれば、通常級や情緒級での学習が可能と判断されるケースが多いです。ただし、IQ値はあくまで1つの数値基準に過ぎないため、子どもの特性や学習の様子、情緒の安定度なども合わせて見ていく必要があります。IQだけに頼るのではなく、複数の観点を総合的に踏まえて判断することが大切ですよ。
入級までに必要な手続きは?
まずは自治体へ相談する
特別支援学級を希望する場合は、まず居住している自治体に相談することが必要です。ここまで紹介してきた判断基準はあくまでも目安であり、実際には地域や自治体ごとに入級の基準や流れが異なります。学校によって設置されている特別支援学級の種類も違うため、通学予定の自治体に確認することで、より正確な情報を得ることができますよ。また、今後の手続きや必要な書類について説明を受けられるほか、就学前相談の申し込みが必要となるケースもあるため、早めに問い合わせてみることが大切です。
検査や面談を通して子どもの様子を確認する

自治体に相談した後は、必要に応じて検査や面談が行われます。特別支援学級に入るためには、各自治体が定める基準を満たしているかどうかを確認する必要があるためです。すでに療育手帳を所持していたり、医師の診断書がある場合には、比較的スムーズに進みますよ。一方で、診断がグレーゾーンだったり、これまで専門機関を受診していなかった場合には、新たに検査を受けるよう求められることもあります。具体的には、IQの測定や子どもの普段の生活、学校での様子についての聞き取り調査などが行われ、総合的に判断されます。
教育支援委員会から就学先の提案を受ける
検査や面談を経て得られた情報は、教育支援委員会などの専門機関で検討されます。教育支援委員会は、医師や心理士、特別支援教育に携わる専門家などで構成されており、子どもの発達状況や学習のつまずき、情緒面の安定度などを総合的に評価します。その上で、通常学級が適しているのか、あるいは特別支援学級や特別支援学校の方が適しているのかを判断し、就学先の提案を行いますよ。最終的な決定権は保護者にありますが、教育支援委員会の提案は子どもの教育環境を選ぶ際の大切な指針となるでしょう。
特別支援学級に入る前にすべきことは?
事前に情報をしっかり確認する

特別支援学級を検討するときには、事前にできるだけ多くの情報を集めておくことが大切です。特別支援学級の制度や内容は自治体ごとに異なり、学校によっても設置されている学級の種類や支援体制が違います。そのため、自治体や学校から配布される資料、公式ホームページなどを確認し、入級条件や手続きの流れを理解しておきましょう。さらに、見学会や説明会に参加することで、実際の学級の雰囲気や先生方の支援の様子を知ることができます。十分な情報を持って判断することで、子どもにとって最適な学びの場を選びやすくなりますよ。
子どもに合った学級の雰囲気かを確認する
特別支援学級を選ぶときは、学級の雰囲気が子どもに合うかどうかも大切な視点です。特別支援学級では、通常学級では受けにくいサポートや療育が受けられますが、必ずしもすべての子どもにとって居心地が良いとは限りません。なかには、大人数の集団の方が安心できる子や、特別支援学級に入ることで自分の障害を意識してしまう子もいますよね。また、特別支援学級によっても、活発な雰囲気のクラスや、落ち着いた雰囲気のクラスなどさまざまです。子どもの性格や特性を踏まえ、無理なく安心して過ごせる学級を選ぶことが、後悔のない進路につながりますよ。
子どもの特性に合った指導内容かを確認する
特別支援学級を選ぶときは、その学級で行われる指導内容が子どもの特性に合っているかどうかも重要な判断材料です。特別支援学級では通常学級とは異なるカリキュラムや支援が用意されていますが、それが子どもの特性をカバーできなければ十分な効果を得られません。例えば、学習面で大きな遅れがないのに、学習支援を中心としたクラスに入ると、合わないと感じることもあるでしょう。指導内容は自治体や学校ごとに違うため、事前によく確認しておくことが大切ですよ。
特別支援学級に入るタイミングは?
特別支援学級があるのは小学校と中学校

特別支援学級が設置されているのは、小学校と中学校です。高校や大学には特別支援学級はないため、その点を踏まえて進路を考える必要があります。幼稚園の頃から発達や行動に気になる様子がある場合は、小学校入学と同時に特別支援学級に在籍する子もいますよ。一方で、発達障害や知的障害は入学時にははっきり表れず、在学中に特別支援学級への入級を希望するケースもあります。学校によっては、通常学級から特別支援学級への変更手続きの方法が異なるため、あらかじめ確認しておくと安心です。
特別支援学級に通った後の進路は?
障害の程度を見て判断する
特別支援学級に入るかどうかは、子どもの障害の程度によっても判断されます。同じ診断名であっても、日常生活や学習にどの程度支援が必要かは子どもによって大きく異なります。軽度であれば通常学級での在籍が可能な場合もありますし、より手厚い支援が必要であれば特別支援学級での学びが適していることもありますよ。大切なのは、診断名だけにとらわれず、実際の生活や学習の様子をふまえて考えることです。保護者や学校、専門機関が連携しながら、子どもにとって安心して成長できる環境を選んでいくことが求められますね。
まとめ
特別支援学級の理解を深めて最適な選択をしよう
特別支援学級は、子ども一人ひとりの特性に合わせて学びや生活を支える大切な場です。知的級や情緒級といった種類の違いや、入級の基準、手続きの流れなどを理解しておくことで、子どもにとってより良い環境を選びやすくなりますよ。大切なのは、障害があるから入るのではなく、その子が安心して成長できる環境はどこかを考えることです。学校や自治体、専門機関と連携しながら情報を集め、子どもの特性に合った学級を選ぶことが、本人の自信や将来の可能性を広げることにつながります。