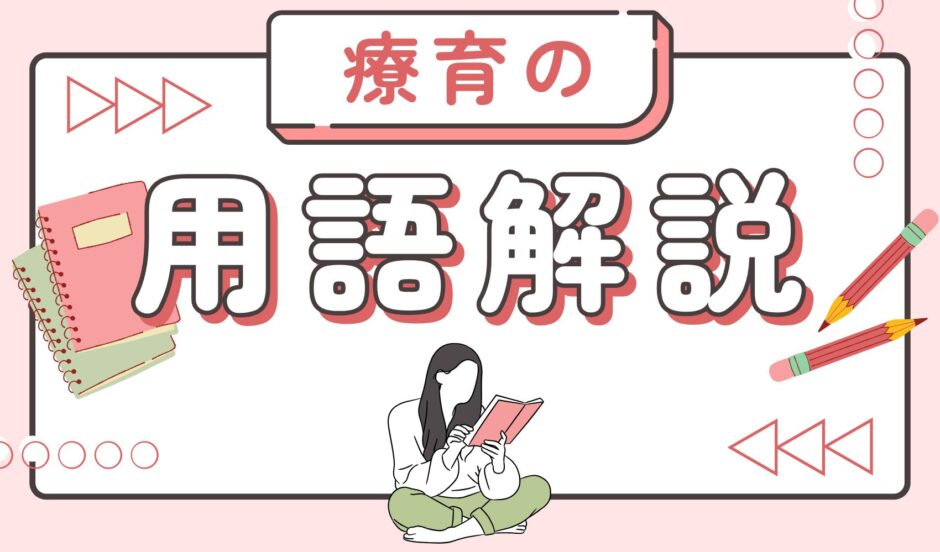療育業務の現場においては、専門的な用語が多く使用されています。中には英語の長い単語を略した略語も多く、療育現場で効率的なコミュニケーションを取るためにはそれらの用語の理解が欠かせません。一方で、療育に携わることがない、または少ない人にとっては聞き馴染みのない言葉も多く、聞いただけでは意味が伝わりにくい言葉もあります。この記事では、療育業務に関わる用語について、良く使われる用語をその意味や略語と併せて紹介していきます。現在療育業務に携わっている人はもちろん、将来的に療育に関わろうと思っている人はぜひ参考にしてみてください。
療育に関する基本用語とその略語
児童発達支援管理責任者(児発・児発管)

まず初めに、療育に関する基本用語とその略語について見ていきましょう。1つ目に紹介するのは児童発達支援管理責任者です。児童発達支援責任者は、障害を持つ子どもたちを支援する施設において、支援内容の責任を持つ立場の人を指します。支援スタッフが行う支援計画の作成や管理を行ったり、保護者と連携を行ったりするのが主な業務です。療育に関する専門的な知識と経験が求められるため、実務研修を受けた後に資格を取得する必要がありますよ。児発管、児発と略されることも多いです。
相談支援専門員(相談員)

相談支援専門員は、施設に通う子どもやその家族に、必要なサービスや支援内容を調整する役割を担います。必要に応じて施設外の医療機関や教育機関と連携を取るのも、相談支援専門員の仕事です。施設で提供する支援サービスの内容だけではなく、障害を持つ子どもに対する全般的な支援相談を担う点が特徴ですよ。児発管と同様に資格が必要ですが、児発管と比較すると、地域全体での支援調整や相談業務のスキルを高めることが重要視されます。相談支援専門員は相談員と言われることが多いです。
児童指導員

児童指導員は、児童発達支援施設や放課後等デイサービスで、障害を持つ子どもに対して日常的な支援や療育を行う役割があります。児発管や相談員が作った個別支援計画書に基づいて、実際の支援を行うのが主な業務内容です。子どもたちと直接関わる機会が多いため、子どもたちと信頼関係を築けるようなコミュニケーション能力が求められます。また、日々の支援の進捗を記録するのも児童指導員の役割ですよ。療育現場において最前線で働くスタッフとも言えますね。
個別支援計画書

個別支援計画書とは、支援が必要な個別の利用者に対して、どのような支援を行うかを具体的にまとめた計画書です。主に障害を持つ子どもや成人が対象で、その人のニーズや特性に基づいて目標を設定し、支援方法やアプローチを明記します。計画書には、支援目標や具体的な支援内容、進捗の評価方法などが含まれ、支援者が実施する支援の方向性が示されますよ。定期的に進捗を確認し、必要に応じて計画を見直して効果的な支援を提供することが目的です。個別支援計画書は主に児発管が作成します。
放課後等デイサービス(放デイ)

放課後等デイサービスとは、主に発達障害や知的障害などの特別な支援が必要な子どもを対象に、学校の授業終了後や長期休暇中に子どもが療育を受けられるサービスです。放デイと略されることも多いです。放課後や休暇期間中、保護者が仕事などで子どもの面倒を見ることが難しい場合に、専門的な療育支援を受けることができます。また、生活支援や社会性を育む活動だけでなく、学習支援を行う施設もありますよ。何人かの子どもと一緒に活動するため、子どもたちが集団生活や対人スキルを学ぶ場にもなります。
療育に関する医療用語とその略語
注意欠如・多動症(ADHD)

注意欠如・多動症とは、注意力の持続が難しく、衝動的な行動や過剰な活動性が特徴的な発達障害の一つです。ADHDと略されることも多く、聞いたことがある人もいるのではないでしょうか。ADHDでは、以下のような症状が見られます。
・集中できない
・忘れ物が多い
多動性の症状
・じっとしていられない
・過度に動き回る
衝動性の症状
・順番を待てない
・思いついたことをすぐに行動に移す
これらの症状は学校や家庭、社会生活に支障をきたすことがありますが、薬物療法や行動療法、個別支援によって改善していくことができますよ。
自閉症スペクトラム(ASD)

自閉症スペクトラム障害は、社会的なコミュニケーションや行動に特有の困難を伴う発達障害です。ASDと呼ばれることもあります。主な特徴としては以下が挙げられます。
(目を合わせにくい、感情の表現が難しいなど)
・反復的な行動
(特定の物や活動に固執する、同じことを繰り返すなど)
・限られた興味
(特定の分野に強い関心を持つなど)
ASDは症状の程度や現れ方が人によって異なり、軽度から重度まで様々ですが、早期の支援や療育によって改善していくことができます。
広汎性発達障害(PDD)
広汎性発達障害は通称PDDとも呼ばれ、主に社会的なコミュニケーションや行動の柔軟性に関する問題が特徴的な発達障害の一群を指します。代表的なものとして自閉症、アスペルガー症候群、レット障害などが含まれ、社会的な相互作用やコミュニケーションの困難、反復的・固定的な行動や興味の傾向などが共通する特徴です。現在では、広汎性発達障害は自閉症スペクトラム障害に統合されることが多いですが、かつては異なる診断名として扱われていました。
学習障害(LD)

学習障害は、知的能力には問題がないにもかかわらず、読み書きや計算などの特定の学習分野で著しい困難を抱える発達障害の一つです。読み書きや計算が困難になる他、注意力や記憶に関連する問題なども学習障害に当てはまる場合がありますよ。学習障害のある子どもは、他の子どもと同じペースで学習することは困難なため、個別の方法やペースで学習支援を行う必要があります。早期に適切な支援を行うことで、学業や日常生活の向上が期待できますよ。
チック症
チック症は、無意識で反復的にある動作や発声を行なってしまう症状のことを指します。目を何度も瞬きしてしまったり、顔をしかめてしまったり、喉を鳴らしてしまったり、などの症状が挙げられます。本人が止めたいと思っていても抑えられないことが多く、子どもによく見られる障害ですよ。治療が必要な場合もありますが、成長とともに軽減することが多いため、軽度であれば特別な治療は必要ないと考えてよいでしょう。
療育に関する業務用語とその略語
ABA

ABAとは、Applied Behavior Analysisの略で、日本語では応用行動分析と言います。行動の変化を促すための科学的なアプローチで、自閉症や多動症などの発達障害を持つ子どもに対する効果的な療法として知られていますよ。ABAでは、どんな行動が発達障害の行動として現れているのかを調べるために、観察と分析をします。その後に、適切な行動に対して報酬を与え、不適切な行動を減らすような働きかけが行われます。継続的な観察とフィードバックに基づいて治療が行われるこの療法は効果が証明されており、特に自閉症の治療で広く活用されています。
PT

PTとは、Physical Therapyの略で、日本語では理学療法と言います。身体の機能や動きを改善するための治療法で、主に怪我や病気、手術後のリハビリテーションに用いられます。理学療法を行う専門家である理学療法士をPTと呼ぶ場合もありますよ。PTでは、患者の状態に合わせた運動療法やマッサージなどを活用して、痛みの軽減や筋力の回復などをサポートする役割を持っています。身体障害や精神疾患に対応する場面で多く使われる用語です。
OT

OTとは、Occupational Therapyの略で、日本語では作業療法と言います。日常生活で必要な動作や活動を改善するための療法で、主に身体的、精神的な障害を持つ子どもが、日常生活の質を向上させることができるようにサポートを行います。PTと同様に、作業療法を行う作業療法士のことをOTと呼ぶこともありますよ。OTは、食事や着替えなどの日常生活を自立して行うために必要な手指の動き、認知機能、コミュニケーションスキルなどの改善を図る治療方法です。特定の動きや課題を用いて訓練を行うことで、それらの活動がスムーズに行えるように働きかけます。発達障害や精神疾患の他、高齢者のケアなどの福祉現場でも多く使われる用語ですよ。
TEACCH

TEACCHは、自閉症の人々を支援するための教育プログラムの名称です。日本語では、自閉症及びコミュニケーションに関連した障害を持つ子どもの治療と教育という意味です。アメリカのノースカロライナ大学で開発されたもので、構造化教育の概念を基本に、それぞれ個々のニーズに合わせた支援を行いますよ。自閉症の人々が混乱することなく環境に適応できるように、明確なスケジュールや指示を示したり、視覚的なツールを活用する点が特徴です。
SST

SSTは、ソーシャルスキルトレーニングの略で、対人関係や社会的な状況で適切に振る舞うためのスキルを向上させる訓練方法を意味します。このトレーニングは、自閉症やその他の発達障害を持つ人々に対して活用されるアプローチです。主に、ロールプレイングや遊びを通じて、会話や感情の表現の仕方、複数人での対話などを円滑に行うための方法を学びます。学校の特別支援教室やカウンセリング、療育現場などでよく用いられる用語ですよ。
アセスメント

アセスメントとは、発達障害を持つ子どもたちの特性やニーズ、問題点を評価するプロセスのことを指します。アセスメントでは、子どもに最適な支援計画を立てるための基礎情報を得るために、子どもたちの行動観察や学習能力を図るためのテスト、保護者からのヒアリングなどが行われますよ。アセスメントによって、その後の療育方針や支援計画が決まってくるため、療育においてはとても重要な取り組みです。療育現場では必ず行うプロセスと言えます。
ペアレントトレーニング(ペアトレ)

ペアトレとは、ペアレントトレーニングの略です。発達障害を持つ子どもの保護者が、子どもへの適切な支援方法を学ぶためのプログラムを指します。療育において、保護者と子どもの関わりはとても重要ですよね。そのため保護者は、子どもの障害について正しく理解をしたうえで、適切な対応方法を学ぶ必要があります。ペアトレでは、療育センターでのカウンセリングや病院の療育部門で、保護者向けのトレーニングが提供されています。
まとめ
療育用語を理解して業務を円滑に進めよう
ここまで、療育に関わる用語について、基本用語や医療、業務で頻繁に使う用語を中心に解説してきました。療育業務に関わる用語には英語や略語も多く、普段の生活では聞きなれない言葉も多いですよね。働いているうちに自然と覚えられる単語もありますが、なかには専門的な用語もあります。療育現場で働いている人、これから働く予定のある人は、それぞれの用語に対して正しい理解をしておくようにしましょう。