あなたは児童発達支援センターがどのような施設なのかをご存知ですか?児童発達支援センターとは、主に障がいのある未就学児を対象に総合的な支援を行う療育支援施設のことです。この記事では、児童発達支援センターの具体的なサービス内容や仕事内容、児童発達支援事業所との違いを解説していきます。児童発達支援センターについて詳しく知りたい方は、ぜひこの記事を最後まで読んでみてくださいね。
児童発達支援センターとは?
障害のある未就学児に総合的な支援を行う施設

児童発達支援センターとは、障がいのある未就学児を対象に専門的な療育支援を提供する施設です。この施設では、自治体に住んでいる障がいのある子どもに日常生活における基本的な動作や、自活に必要な知識や技能の指導、集団生活に適応するための訓練を行います。近年は、需要が高まっている放課後等デイサービスを併用しているような発達支援センターもありますよ。児童発達支援センターには、福祉サービスを提供する福祉型と治療も行う医療型があります。それぞれの詳しい内容もこの記事で解説していきます。
児童発達支援センターの設置基準
人員基準

児童発達支援センターの人員配置の基準は以下のようになっています。
※主たる対象の障害が知的障害の場合は、精神科、難聴の場合は耳鼻咽喉科の診療に相当の経験を有するもの
・児童指導員及び保育士: 4:1以上
・児童指導員:1人以上
・保育士:1人以上
・児童発達支援管理責任者:1人以上
・栄養士:1人以上(定員40人以下の場合は置かないことも可)
・調理員:1人以上(全部委託の場合は置かないことも可)
・機能訓練担当職員:(機能訓練を行う場合)
・看護職員:(医療的ケアを行う場合)
・管理者:(兼務可能)
主として難聴時の場合:言語聴覚士4人以上(単位ごと)
主として重心の場合:看護職員、機能訓練担当職員各々1人以上
参考資料:https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/000994415.pdf
設備基準
児童発達支援センターの設置基準は以下のようになっています。
・指導訓練室:定員おおむね10人
床面積 2.47㎡以上/人
(主として難聴、重心の場合は除く)
・遊戯室:床面積1.65㎡以上/人
(主として難聴、重心の場合は除く)
・屋外遊技場
・相談室
・調理室
・便所
・静養室:(主として難聴、重心の場合は除く)
・その他、指定児童発達支援の提供に必要な施設及び備品等を設けること
・聴力検査室:(主として難聴児が通所の場合)
参考資料:https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/000994415.pdf
運営基準
運営基準とは、サービスの提供にあたって施設で行うべき事項をまとめた基準のことです。児童発達支援センターの運営基準にはさまざまな項目があります。以下は、児童発達支援センターの運営基準の一例です。
(利用定員) 第十一条 指定児童発達支援事業所は、その利用定員を十人以上とする。ただし、主として重症心身障害児を通わせる指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものを除く。)にあっては、利用定員を五人以上とすることができる。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=424M60000100015
児童発達支援センターの対象者は?
障害のある0〜6歳までの未就学児

児童発達支援センターに通うことができる対象者は、下記のとおりです。
・身体の障害、知的障害、発達障害を含む精神障害のある子ども
・医療型の場合は、上肢か下肢または体幹機能に障がいがある子ども
・児童相談所や市町村保健センター、医師等によって療育の必要性が認められた子ども
上記の項目に該当する子どもは児童発達支援センターに通うことができますよ。また、自治体によっては、診断はなくても療育が必要と認められた子どもも対象となります。
児童発達支援センターの役割
療育

児童発達支援センターは、発達に遅れや課題を抱える子どもたちの成長をサポートする重要な役割を担っています。その中でも中心的な役割が、子どもの療育です。療育とは、個々の子どもの発達状況やニーズに合わせた、専門的な支援を提供することです。医師や心理士、言語聴覚士などの専門スタッフが、個別指導や集団訓練を通して、運動機能や認知能力、コミュニケーション能力などの発達を促していきますよ。療育は、単純に知識や技能を身につけるだけでなく、子どもが社会の中で自立して生活していくために必要な自信や意欲を育むことにもつながります。
家族支援

児童発達支援センターは、家族への支援も行っています。家族支援では、子どもの家族が安心して子育てを行えるように物理的、または心理的な支援を行います。具体的な家族支援の例は以下のとおりです。
・定期的に子どもの発達状況や支援内容の確認をする
・家族向けのペアレントトレーニング
・子どもとのかかわり方などに関する相談や助言
このように児童発達支援センターでは、子どもへのサポートだけでなく、家族へのサポートも行っていますよ。
地域支援

児童発達支援センターは、地域支援も行っています。児童発達支援センターの地域支援とは、保育園や幼稚園、病院など、子育てに関わる地域の専門機関と連携し、支援を行うことです。地域の様々な専門機関と連携することで、子ども一人ひとりのニーズに合わせた支援を行うことができるのです。地域全体で課題を共有し、解決に向けて取り組むことで、子どもが安心して成長できる環境を作りますよ。
児童発達支援センターの種類
福祉型児童発達支援センター
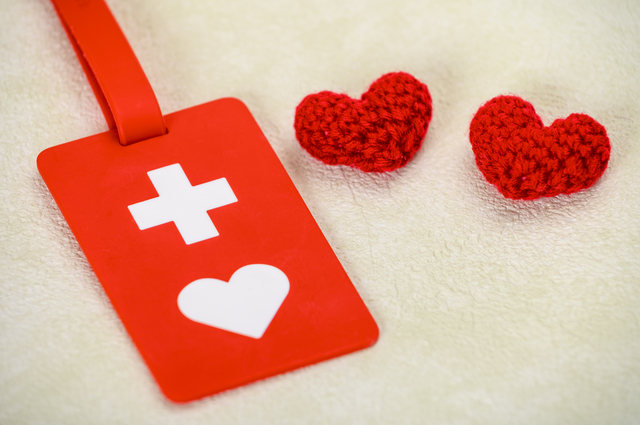
福祉型児童発達支援センターとは、身体や知的、精神に障がいのある児童を対象としている施設です。福祉型児童発達支援センターでは、日常生活での基本的な動作の指導や集団生活になじむための訓練などを行います。また、保育所等訪問支援というサービスも行っていますよ。これは、保育所や幼稚園、学校などの集団生活を行っている施設に訪問して、障がいのない子どもとコミュニケーションをとり集団生活に慣れていくという、専門的な支援です。
医療型児童発達支援センター

医療型児童発達支援センターとは、上肢、下肢または体幹機能に障がいのある児童を対象としている施設です。医療型は福祉型のサービスに加えて、上肢や下肢、体幹機能に障がいのある児童への治療や発達支援も行います。医療型では、理学療法によるトレーニングや利用的管理に基づいた支援に加えて利用者の家族からの相談対応なども行っていますよ。このように、医療型児童発達支援センターでは福祉サービスとともに治療も行うことができるのです。
児童発達支援センターの1日の流れは?
平日
ここでは、児童発達支援センターに勤める職員の1日のおおまかな流れをご紹介します。
子どもの健康状態の確認を行う
9:30〜10:30 自由時間
アセスメントに応じて、遊びの見つけ方や参加の促しなどの支援をする
10:30〜11:40 療育支援
個別の支援計画に基づいて、課題や活動内容を設定して支援を行う
11:40〜12:00 片付け、帰る準備
片付や帰りの準備をするように声掛けをする
12:00〜 子どもの退所
次回の日程や、1日の振り返りを子どもと行う
こちらの1日の流れは一例です。そのため、施設や役職によってプログラムや営業日は施設によって異なります。
休日
休日の場合のおおまかな流れは次のとおりです。
子どもの健康状態の確認を行う
9:30〜10:30 自由時間
アセスメントに応じて、遊びの見つけ方や参加の促しなどの支援をする
10:30〜11:30 療育支援
個別の支援計画に基づいて、課題や活動内容を設定して支援を行う
11:30〜13:00 昼食
できるだけ子どもだけでご飯の用意をできるようにサポートする
13:00〜14:00 集団レクリエーション
知育、療育、体育などの観点から活動内容を決める
14:00〜14:20 片付、変える準備
片付や帰りの準備をするように声掛けをする
14:20〜 子どもの退所
次回の日程や、1日の振り返りを子どもと行う
施設や役職によって1日の流れは異なります。
児童発達支援センターでの仕事内容は?
機能訓練

児童発達支援センターで行われる機能訓練は、子ども日常生活における動作能力の向上させるために行われます。機能訓練は、日常生活における基本的な動作の獲得や、運動機能や感覚機能の発達促進を目的としており、理学療法士や作業療法士などの専門スタッフが指導を行います。機能訓練では具体的に、以下のような指導を行います。
・集団生活に適応するための訓練
機能訓練の具体的なプログラムは、施設によって違いがあります。
個別指導

児童発達支援センターで行われる個別指導は、子どもの発達段階やニーズに合わせた個別プロブラムに基づいて行われます。個別指導は、子どもの発達を促したり、子どもが抱える課題を克服したりすることを目的としていますよ。個別指導は、面談やアセスメントなどをもとにして個別支援計画を作成して行います。この個別支援計画をもとに発達支援や家族支援、地域支援の内容を決定していくのです。
児童発達支援センターの職員配置は?
管理者、児発管、指導員または保育士の配置が必須

児童発達支援センターには、様々な役職の方が在籍しています。その中でも管理者、児発管、指導員または保育士の配置が必須とされています。
児童発達支援管理責任者:児童発達支援に関する専門的な知識と経験を持ち、個別支援計画の作成や指導員の指導などを行います
児童指導員または保育士:お子様一人ひとりの発達段階やニーズに合わせた個別指導や、集団での遊びや活動を通して、社会性を育む支援を行います
これらの職員は、児童発達支援センターの運営と子どもの成長を支える基盤となる重要な役割を担っています。
児童発達支援センターと児童発達支援事業所の違いは?
サービス内容
児童発達支援センターと児童発達支援事業所の1つ目の違いは、サービス内容です。児童発達支援センターは、地域の関係機関と連携を取り、居宅訪問型児童発達支援などの訪問サービスを行っています。一方で、児童発達支援事業所は、もっとも身近な療育の提供してくれる場所として、地域内にたくさんあります。このように、児童発達支援センターには、事業所が提供しているサービスに加えて、訪問支援や支援利用計画の作成などを行っているのです。
規模
児童発達支援センターと児童発達支援事業所の2つ目の違いは、規模の違いです。児童発達支援センターは児童発達支援事業所よりも大型の施設で、ほかの期間や事業が併設されているのです。また、人員基準や設置基準なども異なります。児童発達支援事業所の人員基準として設けられているのは以下のとおりです。
・機能訓練員:(機能訓練を行う場合)
・看護職員:(医療的ケアを行う場合)
・児童発達支援管理責任者:1人以上
・管理者:(兼務可能)
その他の違いについては、以下の資料を見てみて下さい。
資料:https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/000994415.pdf
まとめ
児童発達支援センターは障がいを持つ未就学児へ様々な支援を行っている!

いかがでしたでしょうか?今回は児童発達支援センターについて詳しく解説していきました。児童発達支援センターでは、児発管や児童指導員、保育士などたくさんの職業の方々が協力して、障がいを持つ未就学児はもちろん、家族へも様々な支援を行っています。また、児童発達支援センターには、身体や知的、精神に障がいのある子どもが対象の福祉型と、上肢や下肢、体幹機能に障がいのある子どもが対象の医療型があります。児童発達支援センターに興味が出てきた方は、将来の職場の選択肢としてぜひ考えてみてくださいね。



