皆さんは、多機能型事業所という施設を聞いたことがありますか?多機能型事業所について知らなくても、実は多機能型事業所として運営されている施設を利用していた、ということはあるかもしれませんね。今回は、多機能型事業所とは何か、その他に似た施設との違い、多機能型事業所を運営する際のメリットデメリットなど、多機能型事業所について詳しく解説します。単独型ではなく多機能型として運営することで受けられる特例やメリットは多々あります。事業所の状況や提供するサービスによって、どちらが適しているのかをぜひ考えてみてくださいね。
多機能型事業所とは?
2つ以上の障害福祉サービスを提供する事業所

多機能型事業所とは、2つ以上の障害福祉サービスを提供する事業所のことです。1つのサービスを単体で運営するよりも、利用者の増加や仕事の効率化が見込めるため、事業所の収入増加につながると言われています。多機能型事業所として運営できるサービスは以下の通りです。
- 就労継続支援A型
- 就労継続支援B型
- 就労移行支援
- 生活介護
- 自立訓練(生活訓練・機能訓練)
- 児童発達支援
- 放課後等デイサービス
- 保育所等訪問支援
- 医療型児童発達支援
一体型事業所との違いは?
複数の事業所の監督を一体化して行うのが一体型

一体型事業所は、複数の事業所の監督を一体化して行う事業所のことを指します。多機能型事業所では1つの事業所で多種多様のサービスが提供されています。一方で、一体型事業所ではそれぞれのサービスを提供する複数の事業所が、代表の事業所によって運営されていますよ。また、利用定員や従業員配置についても多機能型事業所と一体型事業所では違いがあります。
| 利用定員 | 従業員配置 | |
|---|---|---|
| 多機能型事業所 | 20人以上が必要 | 事業所全体で常勤1人 |
| 一体型事業所 | 20人以下も可能 | それぞれの事業所に常勤1 |
主たる事業所・従たる事業所との違いは?
両方の事業所で同じサービスを提供する
主たる事業所と従たる事業所とは、異なる場所に設置された2つ以上の事業所で、同一のサービスを一体的に提供するサテライト型の運営形態を指します。これは、利用者の増加などにより既存の事業所では受け入れが困難になった際に、追加で2カ所目以降の事業所を開設することで対応する仕組みです。従たる事業所は主たる事業所の管理下で運営され、管理者の配置要件や設備面の基準が一部緩和されるなど、柔軟な運営が可能となります。
多機能型事業所を運営するための条件は?
条件は6つある

多機能型事業所を運営するには、クリアすべき条件が6つあります。条件の一覧は以下の通りです。
- 利用申込みの調整、職員の技術指導が一体的に行われている
- 職員の勤務体制、勤務内容が一元的に管理されており、必要な場合には事業所間で支援し合える体制が整っている
- 苦情処理や損害賠償に対して、一体的な対応ができる体制ができている
- 事業の目的や運営方針、営業日や営業時間、利用料を定める同一の運営規定が定められている
- 人事、給与、福利厚生などの勤務条件による職員管理が一元的に行われている、事業所間の会計が一元的に管理されている
- 2つの事業所の距離がおおむね30分以内で移動できる距離にあり、サービス管理責任者の業務の遂行上支障がないこと
多機能型事業所に適用される特例は?
利用定員に関する特例

多機能型事業所に適用される特例がいくつかあります。1つ目は、利用定員に関する特例です。事業所全体の利用定員が20人以上の場合、各サービスの最低利用定員数が少なくなります。
| サービスの種類 | 最低利用定員数 | 従来の最低利用定員数 |
|---|---|---|
| 放課後等デイサービス | 5人以上 | 10人以上 |
| 児童発達支援 | ||
| 医療型児童発達支援 | ||
| 生活介護 | 6人以上 | 10人以上 |
| 就労移行支援 | ||
| 機能訓練 | ||
| 生活訓練 | ||
| 就労継続支援A型 | 10人以上 | 20人以上 |
| 就労継続支援B型 |
事業所職員に関する特例
2つ目は、事業所職員に関する特例です。多機能型事業所では、一部の職種において兼務が可能です。雇用する人数を減らせるため、人件費の削減につなげることができるでしょう。
| 児童発達支援管理責任者 | 共に兼務が可能 |
| サービス管理責任者 | |
| 常勤の従業員 | 利用定員数が20人未満の場合、サービス管理責任者との兼務が可能 |
| 児童福祉法に基づいたサービス(放デイなど)であれば事業所間の兼務が可能 |
児童発達支援管理責任者やサービス管理責任者については、以下の記事も参考にしてみてくださいね。
設備に関する特例

3つ目は、設備に関する特例です。すでに単独型で運営している事業所を多機能型に変更する場合、施設の改築や増設が必須だと考えられますよね。実際には、大半の設備はサービスの提供に支障がない範囲で兼用することが可能です。兼用できる設備の例としては、相談室や多目的室、洗面所、トイレなどがあげられます。しかし、訓練室と作業室はサービスごとの設置が必要です。訓練室と作業室以外にも、サービスを提供する上で利便性が悪い場合は追加の設置を検討しましょう。
多機能型事業所を運営するメリット
一貫性のある支援の提供が可能

多機能型事業所を運営するメリットとして、一貫性のある支援の提供が可能であることがあげられます。障害福祉サービスの中には、利用者の年齢や段階によって適応されるサービスが移行する場合があります。関連した分野のサービスを扱う事業所であれば、環境を変えることなく一貫した支援を受けることができるでしょう。通いなれた場所や親しくなった職員がいる環境で継続した支援を受けることで、本人や家族は安心して事業所に通うことができそうですね。
状況の変化による移行がスムーズ
状況の変化による移行がスムーズに行えることも、多機能型事業所のメリットです。特に就労支援では、就労移行支援から就労継続支援へ、就労継続支援B型からA型へなど、本人の状況や意向によって対象となるサービスが変わることがあります。単独型の事業所でサービスを受けていた場合は、事業所ごと変更する必要があるため、サービス移行のたびに手続きを行うのは面倒ですよね。しかし、多機能型事業所であれば再度手続きを行う必要はなく、比較的気軽にサービスの移行を行うことができます。利用者の状況によって最適なサービスを提案することができそうですね。
経営が安定しやすい

事業所を運営する側の1番のメリットとしては、経営が安定しやすいことがあげられるでしょう。サービスの組み合わせ次第では、利用者が同じ事業所を長期利用することが可能です。長期利用者が多くなるほど、経営の安定化が見込めますよ。また、長期利用者の満足度を向上させることで、口コミによる利用者の増加も期待できます。長期利用者が多ければ多いほど口コミが広がりやすく、利用者の家族間で良い評判が伝わりやすくなります。
特例の対象となる

特例の対象となることも、多機能型事業所を運営する大きなメリットです。前述したように、多機能型事業所では利用定員や事業所職員、設備に関することが特例の対象となります。各役職の兼務が可能だったり設備の兼用が可能だったりと、単独型からの移行がしやすいため、多機能型事業所は比較的運営しやすいと言えるでしょう。しかし、運営するサービスが障害者福祉法に基づくサービスなのか、児童福祉法に基づくサービスなのか、あるいはその両方それぞれに基づくサービスなのかによって、特例には細かな違いがあります。自身が運営する事業所がどれに当てはまるのかをしっかりと確認し、特例をうまく活かせるようにしましょう。
開所時間減算をさけられる
最後にあげるメリットは、開所時間減算をさけられることです。児童発達支援事業所や放課後等デイサービスに適応される開所時間減算とは、営業時間が6時間未満の施設に対し、給付される報酬の15%か30%がカットされる制度のことです。2つの事業における営業時間を合算して6時間以上であれば減算対象から外れるため、多機能型事業所にすることで、この制度が適用されにくくなります。給付の加算や減算は、障害福祉施設の運営に大きな影響を及ぼす部分です。多機能型事業所として運営することで、制度の面からも経営の安定化を見込むことができそうですね。
多機能型事業所を運営するデメリット
より安全面への配慮が必要

一方で、多機能型事業所を運営する際にはいくつかのデメリットもあります。1つ目は、より安全面への配慮が必要なことです。多機能型になることで、1つの施設にさまざまな年齢や特性の人たちが集まります。そのため、単独型の場合よりも安全面に注意が必要です。特に、児童発達支援と放課後等デイサービスを組み合わせた多機能型事業所は、0~18歳の子どもたちが利用します。通所する子どもたちは体格や運動機能に大きな差があるため、ケガやトラブルに繋がりやすいでしょう。適切な人員配置を行うことで、事前にトラブルを防ぐことが大切ですよ。
スタッフの負担が大きくなる
2つ目は、スタッフの負担が大きくなることです。前述した事業所職員に関する特例により、2つのサービス間で兼務できる職種があるため、1人の負担が大きくなってしまうことが考えられます。また、幅広い年齢や特性の人を相手にするため、限られた人員のみで運営していくことは困難です。人件費の削減ができていても、利用者の安全確保や満足のいくサービス提供ができていなければ元も子もありません。施設の規模や利用者の状況などを考慮し、十分な人員が確保された状態でサービスの提供を行うようにしましょう。
報酬単価が下がる可能性がある

3つ目は、報酬単価が下がる可能性があることです。多機能型事業所では、提供するサービスすべての総利用定員数によって報酬単価が算定されます。また、国からの給付は、サービスの提供に関わる人やもの、体制を考慮して決められています。多機能型事業所の場合、サービス間での職員の兼務が可能であることから、人件費の削減が可能とみなされ、報酬単価が下がってしまう可能性が考えられるでしょう。報酬単価は事業所の運営に大きく影響するため、事前に試算しておくのがオススメです。
多機能型事業所の運営例
就労支援型多機能型事業所
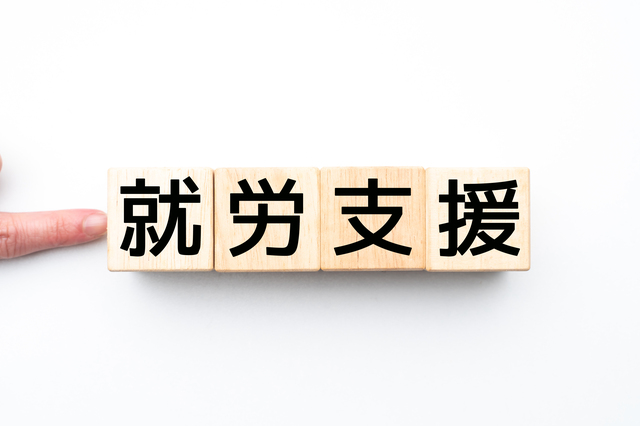
多機能型事業所では、就労移行支援と就労継続支援B型を組み合わせた支援が行われることがあります。就労移行支援は一般企業への就職を目指す人を対象に、職業訓練や面接対策などを提供する一方で、就労継続支援B型は、比較的就労に不安のある人に軽作業などを通じた訓練の場を提供します。例えば、事業所にパン屋を併設して移行支援の利用者が接客やレジ業務を担当し、就労継続支援B型の利用者がパンの製造に携わることで、実践的なスキルを身につけながら自信を育むことができるでしょう。就労移行支援と就労継続支援B型について、詳しくは以下の記事も参考にしてみてくださいね。
児童向け多機能型事業所

児童向け多機能型事業所では、児童発達支援と放課後等デイサービスを組み合わせた支援が行われます。児童発達支援は未就学児を対象に、言語・運動・社会性などの発達を促す療育を提供します。一方で、放課後等デイサービスは就学児に対して、学校後の時間に学習支援や集団活動を通じた社会性の向上を図ります。例えば、午前中は未就学児がリトミックや感覚遊びを行い、午後は小学生が宿題やSST(ソーシャルスキルトレーニング)に取り組むなど、年齢や発達段階に応じた支援を一体的に提供することができますよ。
まとめ
多機能型事業所で効果的・効率的な支援を提供しよう!

いかがでしたか?今回は、多機能型事業所が受けられる特例や多機能型事業所の運営例など、多機能型事業所について詳しく解説しました。多機能型事業所として運営することで、さまざまなサービスをより効率的に行うことができます。一方で、スタッフの負担増加や報酬単価の減少など、事業所を運営する上で悩ましいことも出てくることが考えられますよ。適切な人員配置やしっかりとした試算を行うことで、利用者とその家族が安心して利用できる事業を目指していきましょう!



