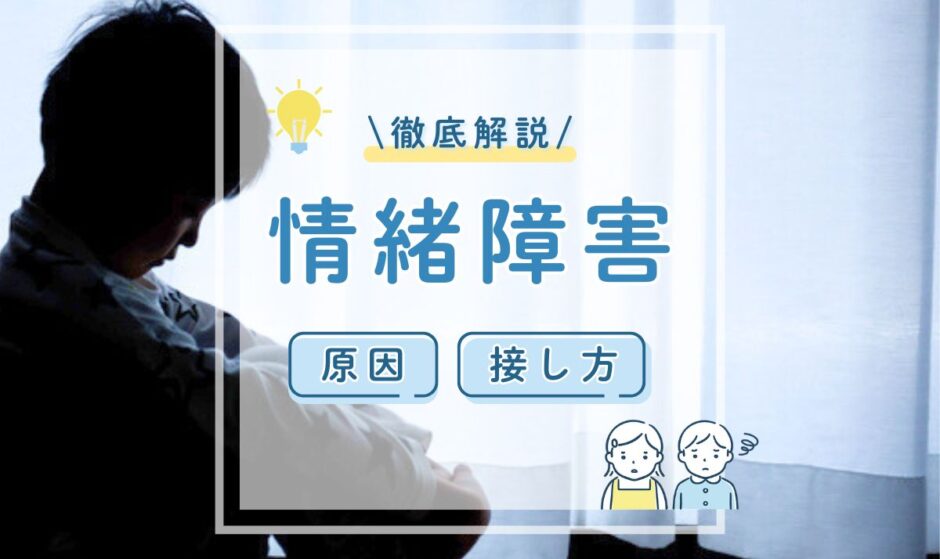保育園などで、子どもが他の子どもよりも落ち着きがなく、すぐ感情的になる場面を頻繁に見ると、心配や不安を抱く保護者は多いのではないでしょうか?こうした子どもの言動は、情緒障害の症状かもしれません。情緒障害は、原因や支援方法などの理解を深めることで、子どもの症状に合った適切なサポートにつなげることができます。今回の記事では、子どもの情緒障害の原因や生じる問題、支援のポイントについて詳しく紹介します。また、子どもの症状に応じた相談窓口も紹介しているので、ぜひ参考にしてみてくださいね。
子どもの情緒障害とは?
感情の調整が難しく日常生活に影響が出る状態
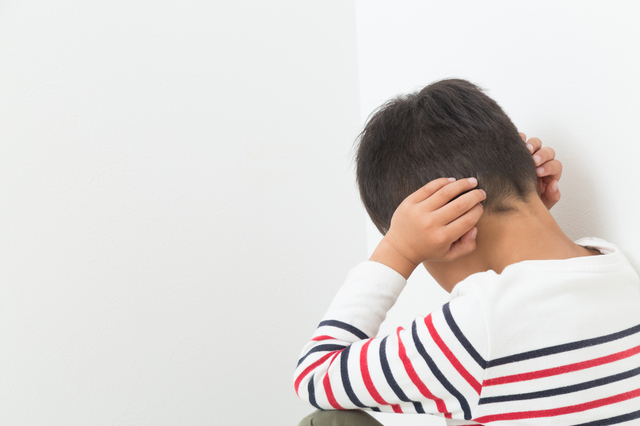
子どもの情緒障害とは、感情の調整が難しく、日常生活や対人関係に支障をきたす状態を指します。例えば、不安や怒りの感情表現が過剰であったり、些細なことで極端に落ち込んだりすることがあります。こうした情緒障害の原因は、遺伝的要因や環境要因、ストレスなど多岐にわたります。このとき、周りの大人が子どもの言動への理解を深めて早期に適切な支援や療育を提供することで、子どもは感情をコントロールしやすくなり、より安定した生活を送ることが可能と言われています。迅速に対応して、子どもの健やかな成長につなげていきましょう。
情緒障害の原因
発達障害による影響
情緒障害の原因の1つに発達障害の影響があります。自閉症スペクトラム症や注意欠如・多動症(ADHD)などの発達障害を持つ子どもは、感情のコントロールが苦手なことが多く、不安や怒りが強く表れやすい傾向があります。他者の感情や意図を読み取るのが難しく、誤解やストレスが増えることで情緒不安定になることもあります。こうした発達障害の特性を理解して適切なサポートを行うことで、子どもの情緒の安定と健やかな成長を促すことができますよ。
心理的ストレスによる影響

心理的ストレスによる影響も、情緒障害の原因の1つとされています。家庭内の不和や過度なプレッシャー、集団生活でのいじめ、環境の変化などが子どもの心に大きな負担を与え、感情の調整を困難にさせます。強いストレスが続くと、不安や怒りを抑えられなくなったり、抑うつ的になったりすることがあります。また、子どもはストレスに対処する力が未発達なため、小さな出来事でも大きな影響を受けやすい傾向です。心理的ストレスを抱えている様子が見られる場合は、安心できる環境と適切な支援を提供しましょう。心の回復と成長の鍵になりますよ。
子どもの情緒障害で生じる問題
拒食や過食など食事の問題

子どもの情緒障害では、拒食や過食などの食事に関わる問題が生じることがあります。例えば、情緒障害から派生した強い不安やストレスが食欲に影響を与えると、食事を極端に制限したり、逆に過剰に摂取したりします。拒食は、人や状況を思い通りに動かしたくなるコントロール欲求や自己否定感と結びつきやすく、過食は不安や孤独を紛らわす手段になりやすい傾向です。これらの問題が長期間続くと、栄養不足や肥満などの健康リスクが高まりますよ。身近な大人による早期の対応と、リラックスして安心できる生活環境の提供が、拒食や過食の改善への重要なステップとなります。
不眠や不規則な生活習慣

子どもの情緒障害が原因で、不眠や不規則な生活習慣が生じることがあります。強い不安やストレスがあると、寝つきが悪くなったり夜中に何度も目を覚ましたりすることがあります。こうした睡眠不足が続くと、さらなる情緒の不安定につながります。また、日中の活動にも影響し、食事の時間が乱れたり、昼夜逆転の生活になることもありますよ。生活習慣の乱れは心身の健康に悪影響を及ぼし、情緒障害を悪化させる要因となるため、安定した生活習慣を整えることが大切です。
チック・髪いじり・爪かみ

子どもの情緒障害によって、チックや髪いじり、爪かみといった無意識の行動が現れることがあります。チックはまばたきや首振りなどの突発的な動きで、不安や緊張が引き金になることが多いとされています。また、髪いじりや爪かみは、ストレスや不安を和らげる自己刺激行動の一つであり、習慣化すると自ら止めることは困難です。これらの行動が長期間続く場合、子ども自身の自信喪失や対人関係の問題が発生するかもしれません。ストレスや不安の原因を汲み取り、安心できる環境と適切なサポートを行うことで、症状の軽減が見込めるでしょう。
対人関係の問題

子どもの情緒障害は対人関係に大きな影響を与えることがあります。感情のコントロールが難しいため、友達や家族との間で衝突が増えたり、些細なことで怒ったり泣いたりすることがあります。また、不安が強いために他者と関わるのを避けたり、反対に過度に依存したりすることもあります。こうした問題が続くと、友人関係がうまく築けず孤立することもあります。こうした問題を抱える子どもは、周囲の理解と適切な支援を受けることで対人スキルを学ぶことができます。周りの大人が根気強く支援を提供し続けることで、次第に友達や家族とも良好な関係を築くことができるでしょう。
不登校

子どもの情緒障害によって、不登校が生じることがあります。集団生活における強い不安やストレスにより、学校に行くこと自体が苦痛になり、登校を拒否するようになるのです。例えば、対人関係の不安や集団生活への適応困難、学校のルールへの強い抵抗などが要因になることがありますよ。また、感情のコントロールが難しく、些細な出来事で大きく動揺することも影響します。このとき、大人が抱える焦る気持ちを優先して子どもを無理やり登校させるのは避けましょう。まずは子どもの気持ちに寄り添い、深い理解と適切な支援を行います。そして、子どもが安心できる環境を整え、少しずつ社会とのつながりを取り戻すことが重要です。
虚言癖
子どもの情緒障害の影響で虚言癖が生じることがあります。これは、不安や自尊心の低さ、周囲の期待に応えたい気持ちなどが原因になることが多いと言われています。例えば、叱られることを恐れて嘘をついたり、注目を集めるために話を誇張したりします。虚言が習慣化すると、他者との信頼関係の崩壊や社会的な問題につながる可能性がありますよ。そのため、周囲の大人は子どもの嘘を責めるのではなく、プレッシャーのない安心できる環境を整えて、正直に話せる関係を築くことが重要です。
自傷行為
子どもの情緒障害により、自傷行為が生じることがあります。子どもは強い不安や怒り、抑うつ感などを抱えても、感情をうまく表現できません。そのため、抱えている苦しさを和らげる手段として自傷行為に走ることがあるのです。具体的には、腕を引っかく、叩く、物に頭をぶつけるなどの行為が見られます。このとき、周囲の理解が不足していると、子どもはさらに精神的な孤立に陥り症状が悪化することもあります。身近にいる大人は、子どもの心の痛みに気づき、安全な環境で適切な支援を行いましょう。心の回復のために子どもに寄り添うことが重要です。
情緒障害の子どもに対する支援のポイント
変わらないルーティンを作る
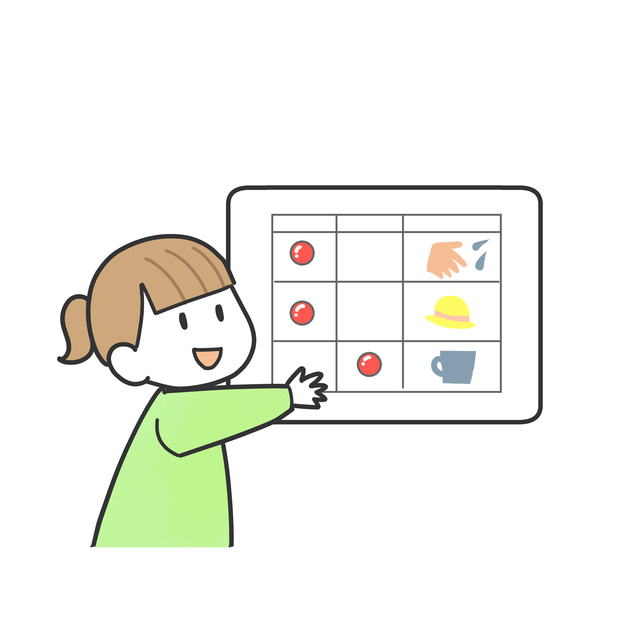
情緒障害の子どもに対する支援では、安定した環境を提供することが大切です。そのためには、変わらないルーティンを作ることが効果的と言えます。毎日の生活の流れを一定にすることで、子どもは安心感を得やすくなり、不安や混乱を減らすことができますよ。例えば、朝の支度や学習の順番、休憩の時間などを決めておくと、見通しが立ちやすくなります。また、ルーティンを維持することで自己管理の力も育まれ、社会生活への適応を助ける効果も期待できるでしょう。
感情を否定しない
情緒障害の子どもに対する支援では、感情を否定しないことが大切です。子どもが怒ったり悲しんだりしたときに、「そんなことで怒らないで」「泣かないで」などの否定的な言葉をかけると、子どもは自分の感情を表現してはいけないと感じ、自己否定につながることがあります。まずは「そう感じたんだね」と受け止め、共感を示しましょう。その上で、適切な表現方法や対処法を一緒に考えることで、自己理解が深まり、感情のコントロール力が育ちます。心から安心できる環境が、子どもの健やかな成長を支えますよ。
解決策を一緒に考える

情緒障害の子どもへの支援では、解決策を一緒に考えることが重要です。子どもが困難に直面したとき、まず気持ちを受け止め、共感を示すことで安心感を与えます。その上で、一方的に解決策を提示するのではなく、いくつかの選択肢を示しながら子ども自身で解決策を考えられるように話し合いをします。自分で決めて成功する体験を積み重ねることで、自己解決能力を高めることにつながります。大人が伴走者となり、共に解決策を見つけることで自信を育み、子どもの成長を支えることができますよ。
専門家に相談する

情緒障害の子どもへの支援では、専門家への相談が重要です。例えば、臨床心理士や特別支援教育の専門家は、子どもの情緒的な課題を理解した上で、適切な支援策の提案ができます。早期に専門家の助言を受けることで、周りの大人は子どもに合った対応を見つけやすくなり、子どものストレスの軽減にもつながりますよ。また、学校や家庭だけでなく、医療機関や福祉サービスと連携することで、より包括的な支援が可能になります。子どもの成長を支えるためには、適切な相談先を見つけることが大切ですね。
保護者も穏やかでいられる環境を作る

情緒障害の子どもを支援する際、保護者が穏やかに過ごせる環境を整えることも重要です。保護者の精神的な安定は、子どもの安心感や情緒の安定につながります。そのためには、学校や支援者は保護者と定期的に連携して、悩みを共有できる場を設けることが大切です。また、保護者がリフレッシュできる時間を確保するための支援も有効ですよ。地域の支援機関や専門家と協力しながら、保護者が孤立せずに安心して子育てできる環境を整えていきましょう。
子どもの情緒障害の相談窓口
身体症状が強い場合は小児科
子どもの情緒障害に伴い、頭痛や腹痛、吐き気、食欲不振などの身体症状が強く現れることがあります。これらの症状が続く場合、まずは小児科を受診して身体的な病気が隠れていないかを確認しましょう。小児科では必要に応じて専門医や心療内科、小児精神科への紹介も行われます。情緒的な問題が原因と考えられる場合でも、適切なサポートを受けることで症状が和らぐことがありますよ。早めの受診が、子どもの心と体の健康を守る第一歩となります。
情緒面の問題が強い場合は児童精神科
子どもの情緒面の問題が強い場合は、児童精神科を受診して専門的なアドバイスと支援を受けましょう。児童精神科は、情緒障害や不安、うつ、対人関係の困難などに対して診断や治療を行う医療機関です。特に、日常生活に支障をきたすほどの情緒不安定が見られる場合は、早めの受診が望ましいです。児童精神科では、カウンセリングや薬物療法、環境調整のアドバイスなどを通じて、子どもが安心して生活できるように支援します。児童精神科の受診を迷う場合は、まずは学校や自治体の子育て相談窓口に相談するとよいでしょう。
児童精神科についての詳しい内容はこちらの記事を参考にしてみてください。
まとめ
1人で抱え込まず専門家に相談してみよう

いかがでしたか。今回の記事では、子どもの情緒障害の原因や生じる問題、支援のポイントについて詳しく紹介しました。子どもの情緒障害は、感情の調整が難しく日常生活に悪影響が出る状態を指します。子どもの情緒障害の支援には、子ども自身のケアだけではなく、保護者へのサポートを行い精神面の安定を確保することも非常に重要です。子どもの情緒障害で悩んでいる方は1人で抱え込まず、まずは専門家に相談してみましょう。今回の記事で紹介した相談窓口も、ぜひ参考にしてみてくださいね。