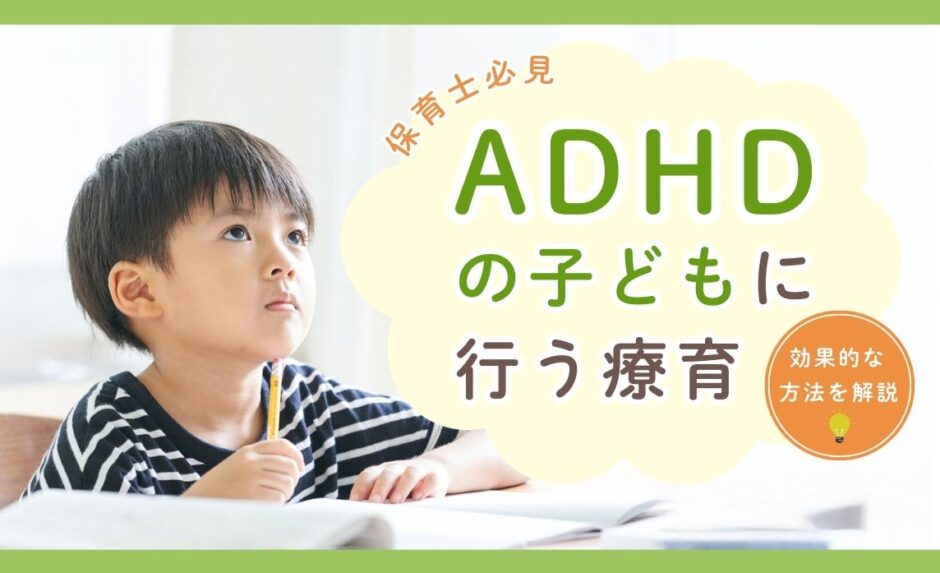ADHDの子どもはどのような療育を受けられるのでしょうか。今回の記事では、ADHDの子どもたちが受けられる運動療育や感覚統合訓練、SSTなど、療育の具体的な方法と例を紹介しています。専門的な施設だけでなく、家庭や保育園でも実践できる療育を紹介していますよ。子どもの発達特性を理解して、周囲と協力しながら子どもの力を伸ばしていきましょう。ADHDの子どもへの療育について知りたい保育士さんに、ぜひ読んでいただきたい記事です。ご参考にしてみてくださいね。
ADHDとは?
不注意・多動性・衝動性が主な症状の発達障害

ADHD(注意欠如多動症)とは、不注意や多動性、衝動性が症状の発達障害です。これらの症状は年齢や環境によって現れ方が異なり、学業や仕事、人間関係に影響を及ぼすことがありますよ。例えば、不注意により物をなくしやすかったり、指示に従うのが難しかったりします。また、多動性や衝動性は、落ち着きのなさや順番を待てない行動として現れます。適切な支援や治療を受けることで、本人の特性に合った生活を送ることができます。
ADHDにむけた療育の目的とは
適切な発達を促し生活環境を整える
ADHDに向けた療育の目的は、本人の特性を理解し、適切な発達を促すことにあります。ADHDの子どもは、不注意や多動、衝動性といった特性が日常生活や対人関係に支障をきたすことがあるため、療育で自己コントロール力や社会性を育てていきます。また、本人の特性に合わせ生活環境を整えることも重要ですよ。例えば、静かな学習スペースを用意したり、スケジュールを可視化するなど、集中しやすい環境を作ることで本人の負担を軽減できます。
ADHDに効果的な療育①運動療育
脳を活性化させる運動療育が効果的

ADHDに効果的な療育の一つに運動療法があります。運動には脳の働きを活性化させる効果があり、特に集中力や衝動のコントロールを高めるのに有効とされています。有酸素運動やバランス運動、リズム運動などは、注意力や身体の自己制御能力を養うのに役立ちますよ。また、体を動かすことでストレスの発散、情緒の安定に繋がります。運動療法は本人が楽しみながら取り組めることが多く、継続しやすいという利点があります。専門家の指導のもと、個々の発達段階に応じたメニューを取り入れることで、ADHDの特性を前向きに活かす支援が可能になるでしょう。
ダンス
ADHDに効果的な療育の一つとして、ダンスがあります。楽しみながら集中力やリズム感、自己表現力を育むことができます。振付を覚える過程では記憶力や注意力が必要とされるので、認知機能のトレーニングにもなりますよ。また、グループで踊ることで社会性や協調性を育む機会にもなり、他者との関わりを学ぶ良い場となります。ADHDの特性に合わせて自由度の高い動きを取り入れることで、成功体験を積みやすく、自信を育てることもできます。
ボール遊び
ADHDに効果的な療育の1つとしてボール遊びがあります。キャッチボールをしたり、大人数で遊ぶ場合はドッヂボールをしたりしましょう。発達特性のある子どもの中には、ターゲットを目で追い続けることが難しい子どもがいます。遊びながらボールを目で追い続けることで、この力を鍛えることができます。また、ボール遊びは、目で字を追って文字を読んだり、はさみを使う練習になりますよ。また、発達特性のある子どもは身体をコントロールして動かすことが苦手な場合があります。身体を動かす遊びで身体をコントロールする力も養いましょう。
ADHDに効果的な療育②感覚統合訓練
様々な素材の上を歩く

人間には合計7つの感覚があります。まず、広く知られているのが五感(視覚・聴覚・触覚・聴覚・味覚・嗅覚)です。さらに、固有受容覚(筋肉や関節、腱からの情報を感じ取る感覚)と前庭覚(重力や頭の動き、バランスの感覚)という2つの感覚があります。感覚統合訓練とは、これら7つの感覚から入ってくる情報を適切に処理し、整理する訓練です。感覚統合訓練の一例として、様々な素材の上を歩くことが挙げられます。マットや人工芝、プチプチ、ザラザラとした布やスポンジ、砂などの異なる質感の素材を床に並べ、裸足で歩きます。これは、足の裏からの触覚や固有受容覚を刺激し、体のバランス感覚や空間認知の力を高める目的で行われますよ。
不安定な場所を歩く
不安定な場所を歩く訓練で、子どものバランス感覚を育てましょう。例えば、バランスボードやクッション、丸太状の柔らかい器具など、足元が不安定な場所を慎重に歩くことで、体幹の安定や姿勢保持、注意力の向上につながりますよ。転びそうになる感覚を経験しながら、自分の体をどうコントロールすればよいかを学びます。特に多動傾向や姿勢が崩れやすい子どもには効果的です。保育士は、必要に合わせて子どもと手をつないだり、体を支えてあげたりしましょう。
ADHDに効果的な療育③SST(ソーシャルスキルトレーニング)
生活スキルを身につけるトレーニング
ADHDに効果的なSST(ソーシャルスキルトレーニング)という療育について紹介します。SSTとは、あいさつの仕方や順番待ちの練習、グループでのルール理解など、生活に必要なスキルを身に着けるためのトレーニングのことです。SSTは、ロールプレイやゲーム形式を取り入れながら、子どもが楽しく学べるよう工夫されています。特にADHDの子どもは、衝動的な行動や注意の散漫さから対人関係で困難を抱えやすく、SSTによって適切な反応や行動パターンを身につけることで、社会性の向上が期待されますよ。継続的な練習とフィードバックを通じて、自信や自己肯定感も育まれていくのです。
①説明

ADHDの子どもは情報の取捨選択が苦手な傾向があります。耳だけで説明を聞いて理解することが困難な場合があるため、SSTを説明する際は図や写真を用いて視覚情報からも理解できるように工夫しましょう。このとき、重要な情報とそうでない情報を分けるため、できる限り言葉をシンプルなものにし、短文で話すことを心がけます。また、ADHDの子どもは細かな説明をつなぎ合わせて自分で全体像を把握することが苦手なので、最初に全体的な流れを説明した後に細かな説明を行うよう心がけましょう。
②お手本を見せる
SSTのお手本を見せるときは、説明をしながら実演してみせます。このとき、いい例と悪い例をセットで実演して子どもの理解を深めましょう。実演するときは簡単な言葉を使い、身振り手振りを使ってわかりやすく伝えることが大切ですよ。例えば「順番を守る」SSTを実演するときは、1人の保育士がおもちゃを使い、もう1人の保育士が順番を待っているというロールプレイを行います。順番を待ち、おもちゃを受け取って仲良く過ごすことができた例、おもちゃの順番を待てずケンカになった例をそれぞれ演じてみましょう。お手本を見せたら、子どもたちが理解できたかを確認し、理解不足な場合は繰り返し実演しましょう。
③子どもにやってもらう
SSTの説明とお手本を見せたら、次は子どもに実践してもらいましょう。例えば「順番を守る」SSTを実践する場合は、子どもたちに2人1組を作ってもらい、1人の子どもがもう1人の子どもに「おもちゃ貨して」と頼みます。頼まれた子どもは「いいよ」と言っておもちゃを渡します。その後、渡してもらった子どもは「ありがとう」とお礼を言いましょう。そして役割を交代し、同じやり取りをもう一度繰り返します。順番を守る流れややり取りの基本を身につけることができますよ。
➃フィードバック
子どもに実践してもらった後はフィードバックを行います。保育士は基本的にそれぞれの実演に対し良かった点を伝えていきます。「ありがとうって言えて偉かったね」というように、細かいところも積極的に褒めましょう。改善点は、「おもちゃが欲しいときはお友達になんて言えばいいんだっけ?」というように、できなかったことを強調するのではなく、次はどうするべきか子どもたち自身で考えられるように伝えましょう。

⑤日常生活に活かす
①~➃までの流れで実施したことを、日常生活に活かしてもらいましょう。何度も反復してその行動をとることで、身についたスキルが少しずつ子どもの中に定着していきます。保育士は、子どもがSSTで学んだ行動を実際の生活場面で使えたときに、すぐに気づいて声をかけることが大切です。「今、順番守れたね」「ありがとうが言えたね」と具体的に伝えることで、子どもは自信を持ち、次も同じ行動をしようという意欲につながりますよ。身についたスキルをノートなどに記録しておき、できたことを家族にも褒めてもらいましょう。
ADHDに効果的な療育➃アンガーマネジメント
怒りの感情をコントロールする
ADHDに効果的な療育として、アンガーマネジメントが挙げられます。ADHDの子どもは感情が沸き上がるとすぐに態度に出すため、怒りの感情を適切にコントロールする方法を学ぶ必要があります。子ども向けのアンガーマネジメントでは、怒りの対象から気をそらすことが重要です。一度その場から離れる、深呼吸する、水を飲むなど、怒りを落ち着かせる行動を見つけましょう。子どもが癇癪を起こしていたら、保護者や保育士が「ちょっとお水のもうか」とサポートしましょう。繰り返していくうちに、自分自身で怒りを他の行動に変えることができるようになっていきますよ。
ADHDの子どもの保護者への訓練
ペアレントトレーニング

ADHDの子どもだけでなく、その保護者が訓練を受けることで、子どもが過ごしやすい環境を整えることができますよ。このトレーニングをペアレントトレーニング(ペアトレ)と言います。ペアトレは子どもの行動変容を目的としており、増やしたい行動は褒める、減らしたい行動は無視をする、やめさせたい危険な行動は叱るというトレーニングをします。保護者は褒め方や罰の与え方を学ぶことで、子どもの行動を制御できるようになりますよ。
ADHDの子どもが療育を受けられる施設
児童発達支援センター
ADHDの子どもが療育を受けられる施設として、児童発達支援センターがあります。児童発達支援センターとは、障害のある未就学児(0歳~6歳)を対象に、専門的な療育支援を行う施設です。児童発達支援センターには身体、知的、精神的なサポートを行う福祉型と、上肢、下肢、体幹に障害を抱える子どもたちに向けた医療型の2種類があります。ADHDの子どもは、福祉型の施設に通うことで個別支援、学校や他の施設との連携、家族へのサポートなどを受けることができますよ。
放課後等デイサービス

ADHDの子どもが療育を受けることができる施設には、放課後等デイサービスも挙げられます。放課後等デイサービスとは、主に障害のある小学生から高校生の子どもたちを対象に、放課後や学校休業日に支援を行う福祉サービスです。ADHDの子どもたちには宿題や勉強のサポート、体を動かすプログラムを提供しています。また、通所する幅広い年齢の子どもたちとのかかわりを通して、思いやりや社会性を獲得することができますよ。
まとめ
療育と周囲の協力でADHDとうまく付き合おう
ADHDとは脳の発達特性であり、生まれ持った性質です。早期に療育や適切な支援を受けることで、子ども自身が自分の特性を理解し、困りごとに対処する力を身につけることができます。もし子どものADHDが分かったら、保護者や保育士は子どもの個性を受け入れ、温かく見守りながら適切な療育と支援を行いましょう。適切な療育と周囲の協力があれば、将来的な自立と社会参加を目指すことはもちろん、子どもの個性を伸ばし社会で活躍することができるようになりますよ。