近年、発達に特性のある子どもへの支援の重要性が高まる中で、療育の役割が注目されています。療育とは、障害のある子どもたちの発達を支援したり、将来社会的に自立した生活を送れるようにサポートすることです。保育士としても、療育の知識を持つことで子ども一人ひとりに適した関わりができ、より良い支援が可能になりますよ。今回の記事では、療育の概要や施設、支援を受けるまでの流れや子どもへの接し方などついて詳しく紹介します。ぜひ今後の保育の参考にしてみてくださいね。
療育とは
障害のある子どもの支援を行うこと

療育とは、障害のある子どもたちの発達を支援したり、将来的に自立した生活を送れるように援助する総体的な取り組みのことです。定義自体は時代とともに変化しており、明確なものはありません。療育という言葉は過去には、身体的な障害がある子どもへの治療と教育に対して使われる言葉でした。しかし、現在では障害のある子ども全般に対する支援の取り組みを指すようになりました。また、療育と言う言葉から、障害のある子どもの治療を思い浮かべる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、発達障害は脳の問題により発症しますが、その仕組みについては未解明な部分が多く、完全に治療することは難しいとされています。そのため、療育では子ども一人ひとりが抱える課題の改善に取り組むとともに、子どもの特性に応じた個別の発達支援を行います。
療育を受けられる施設
通所型
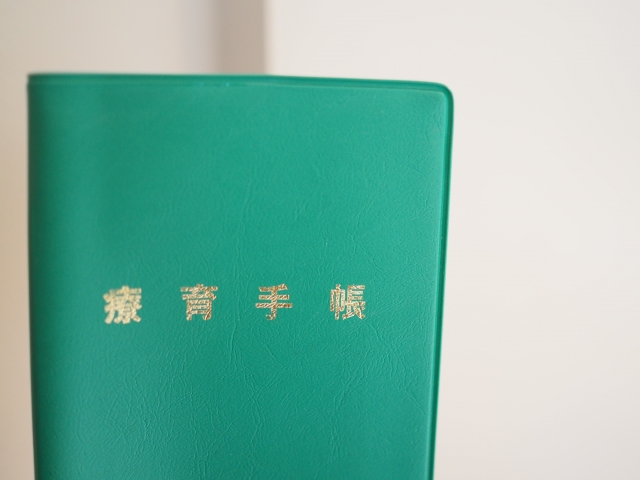
通所型の施設には、福祉型児童発達支援や医療型児童発達支援、放課後等デイサービスや保育所等訪問支援などがあります。具体的な内容は以下の通りです。
・医療型児童発達支援…身体機能に障害のある子どもを対象とし、機能訓練の提供も行う
・放課後等デイサービス…就学している障害のある子どもを対象とし、放課後や長期休暇期間にサービスを提供する
・保育所等訪問支援…スタッフが保育所や学校へ訪問し、サポートを行う
入所型
入所型の施設には、福祉型障害児入所施設と医療型障害児入所施設の2つがあります。福祉型障害児入所施設とは、障害のある子どもが長期間生活しながら療育や生活支援を受ける施設です。主に知的障害や発達障害がある子どもを対象とし、生活スキルの向上や社会性の発達を促すための支援が行われますよ。医療型障害児入所施設は、重症心身障害児や医療的ケアが必要な子どもを対象とし、医療と療育の両面から支援を行う施設です。看護師や医師が常駐し、日常的な医療ケアを提供しながら、子どもの発達を促す療育プログラムが実施されます。
療育を受けるまでの流れ
STEP 1. 相談する
まずは、療育の必要性を確認するために 自治体の福祉窓口や児童相談所、発達支援センターなどに相談しましょう。保育園や幼稚園、学校の先生や医療機関から療育を勧められるケースもあります。このとき、子どもの発達について専門家と話し合い、適切な支援を受けるための方向性を決めることが重要です。また、自治体によっては療育の手続きが異なるため、利用可能な施設や支援内容についても確認しておきましょう。
STEP 2. 検査を受ける
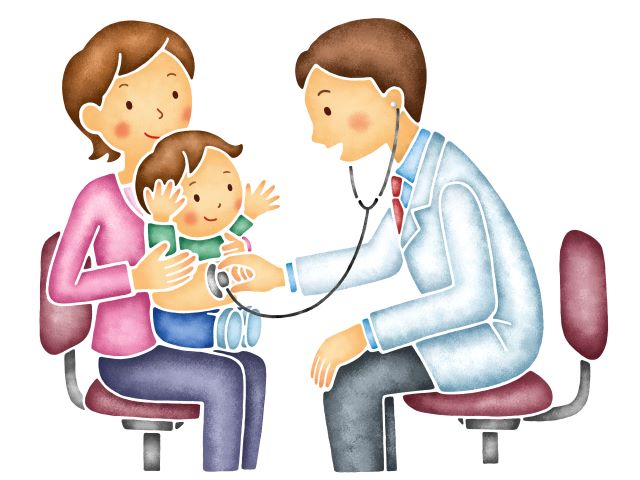
相談をして検査を受けるように勧められた場合や、保護者の判断で必要だと判断した場合には、発達検査や知能検査を受けてみましょう。発達検査の結果が、発達障害の確定診断を行うべきか療育を受ける必要があるかどうかの判断材料になります。また、子どもに合った接し方や支援方法を見つけるためのヒントになりますので、必要があれば発達検査や知能検査を受けてみましょう。ちなみに、発達障害の確定診断を受けるかどうかは自由に選択することが可能です。また、確定診断がなくても療育を受けることはできます。そのため、確定診断は受けない方針の家庭でも、子どもの特性の把握や改善のために、まずは検査を受けることをおすすめします。
STEP 3. 通所の申し込み
療育を受けるには通所受給者証という証明書が必要です。通所受給者証とは、療育などの福祉サービスを受けるために、自治体から交付される証明書のことです。通所受給者証があれば療育施設への通所や入所の申し込みが可能になり、サービスへの自己負担額が1割になります。通所受給者証は療育手帳や発達障害の確定診断がなくても申請が可能です。そのため、療育が必要と判断された場合には、必要な書類(医師の診断書や医療機関等の意見書、サービス等利用計画案など)を揃えたうえで申請するようにしましょう。
STEP 4. 通所受給者証の交付後に施設利用開始
提出書類に基づいて行う調査員とのヒアリングを経て、療育を行う必要があると判断されれば、通所受給者証が交付されます。交付された後は障害児支援利用計画を作成します。交付された通所受給者証と作成した障害児支援利用計画を提出して施設と契約が結ばれると、療育施設で療育を受けられるようになりますよ。このように、療育を受けるまでにはいくつかのステップがあります。早めに相談して適切な支援を受けることで、子どもの成長をより良い形でサポートすることができますね。
代表的な療育プログラム
応用行動分析

行動分析学では、人間の行動や感情は個人と環境の相互的な作用があると考えられています。こうした考えのもとで人間の行動を分析し、法則を明らかにすることが行動分析学の目的です。そうした行動分析をもとに、社会的な問題とされる行動を解決するのが応用行動分析学と言われています。応用行動分析学は療育にも取り入れられており、子どもの問題行動に対して個人の要因と環境の要因を踏まえて対応します。例えば、子どもが人の話や学習に集中できず日常的に問題が生じている場合には、気が散って集中できない要因を取り除いたり、集中が出来たらご褒美をあげたりするなどの対応を取り入れますよ。
TEACCHプログラム
TEACCHとは、1972年からアメリカのノースカロライナ州で実施されている、自閉症スペクトラム障害の子どもやその家族を対象とした支援プログラムです。自治体や支援団体が研究機関と連携しながら、自閉症の子どもとその家族の生活を生涯にわたって包括的に支援するのがTEACCHの特徴です。実際に行われている具体的な手法として、構造化が挙げられますよ。構造化とは、今起きていることや次に起きること、自分がやるべきことを明確にするために、周囲の環境や自分の頭の中を整理することを指します。主な取り組みは以下の通りです。
・活動と場所の対応付け(ex. 勉強する場所・遊ぶ場所をきっちりと決める)
構造化によって子ども自身が周囲の状況や次にやるべきことを認識することで、混乱を防ぎ心理的な安定を得ることができます。
認知行動療法
認知行動療法(CBT)は、認知と行動にアプローチして、ストレスや不安を軽減する精神療法の一種です 。療育の現場では自閉スペクトラム症(ASD)や注意欠如・多動症(ADHD)の子どもが、状況を適切に判断して行動できるように支援する際に用いられます。この療法では、考え方を変えることで気持ちや行動も変えられることを学びますよ。例えば、友達に無視されたと感じても、たまたま気づかなかったのかもしれないと考え直すことで、不安や怒りを抑えて適切な対応ができるように促します。また、療育ではロールプレイやイラストを使ったトレーニングを通じて、ポジティブな思考パターンを身につけることを目指します。
箱庭療法

箱庭療法は、子どもが砂の入った箱の中にフィギュアやおもちゃを自由に配置しながら、無意識の感情や考えを表現する療法です。特に、言葉でのコミュニケーションが苦手な子どもに適しており、感情の整理や自己表現の促進に役立ちます。療育の場では、子どもが作った箱庭を専門家が観察して、その配置やテーマから子どもの心理状態を読み解きます。箱庭の世界を通じて自己理解が深まり、ストレスの発散や安心感を得ることができますよ。また、繰り返し行うことで、内面の変化や成長を確認することができるため、長期的な支援にも適しています。
療育に関わる職業
児童発達支援管理責任者(児発管)
児童発達支援管理責任者(児発管)は、保護者との面談を通じて子どもの発達課題を把握し、個別支援計画を作成します。また、療育施設の中心的な役割を担いながら、子ども一人ひとりに合った療育を提供する責任者です。さらに、療育プログラムの進行を管理し、保育士や療法士などの職員と連携しながら支援の質の向上を目指します。児童発達支援管理責任者には、発達障害や知的障害のある子どもへの支援経験が求められているため、専門的な知識やスキルを備えた人材が活躍できる職業ですよ。
保育士

療育施設で働く保育士は、一般的な保育園や幼稚園と異なり、発達障害や知的障害を持つ子どもの特性に合わせた関わりが求められます。例えば、視覚的支援(イラストや写真を使った指示)を活用したり、感覚遊びを取り入れて発達を促したりします。保育士は、子ども一人ひとりの特性に応じた支援を行うために、発達障害の知識やコミュニケーション技術を身につけることが重要ですよ。また、保護者への助言やサポートを行い、家庭と連携しながら子どもの成長を支える役割も担っています。
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士
理学療法士は、運動機能や身体のバランスの発達をサポートする専門職です。歩行訓練や筋力強化、姿勢の改善などを通じて、子どもが日常生活をより自立して送れるように支援します。作業療法士は、手先の動作や日常生活動作の向上を目指した訓練を行う専門職です。例えば、鉛筆を正しく持つ練習やボタンの留め外しなどの細かい動作を支援して、生活の質を高めるサポートをしますよ。言語聴覚士は、発話や言葉の理解、飲み込み(嚥下)の支援を行う専門職です。発音が不明瞭な子どもや言葉の発達が遅れている子どもに対し、適切なトレーニングを提供します。また、コミュニケーションが苦手な子どもには、ジェスチャーや視覚的サポートを活用した指導を行うこともあります。
臨床心理士・公認心理士
臨床心理士・公認心理士は、子どもの心理的な側面に焦点を当てて、情緒面の安定や行動の改善をサポートする専門職です。発達障害を持つ子どもは不安やストレスを感じやすいため、カウンセリングを通じて自己肯定感を高めて適切な感情表現ができるように支援します。また、認知行動療法や箱庭療法などの心理療法を活用し、子どもの問題行動や不安の軽減を目指すこともあります。保護者への心理的サポートも重要な役割の一つであり、子どもだけでなく家族全体の負担を軽減するための対応も行いますよ。
療育での子どもへの接し方
ポジティブな言葉かけ

療育では、子ども一人ひとりの特性に寄り添いながら、成長をサポートする関わり方が重要です。特に、子どもの自己肯定感を高めつつ安心して学べる環境を作ることが、療育の効果を向上させる鍵となります。例えば、子どもの努力や成果を認めてポジティブな言葉かけをすることで、子どもの自己肯定感を育むことができますよ。「さっきより上手になったね」「一生懸命やっているのが伝わるよ」と、具体的に褒めることで子どもは自身の成長を実感し、自信を持つことができるでしょう。
療育での仕事のやりがい
子どもの成長を感じられる
療育の現場で働く最大のやりがいは、子どもたちの成長を間近で感じられることです。最初はうまくできなかったことが少しずつできるようになり、笑顔が増えていく姿を見ると大きな喜びに感じるでしょう。自身の言葉がけや支援の工夫によって、子どもが「できた!」と自信を持つ瞬間に立ち会えることは、何にも代えがたい経験ですよ。一人ひとりのペースに寄り添いながら成長を支え、その変化をともに喜べることが、この仕事の大きな魅力と言えますね。
まとめ
療育について理解して仕事の可能性を広げよう!

保育士として働く中で、発達に特性のある子どもと関わる機会は少なくありません。療育について理解を深めることで、子ども一人ひとりに合った適切な関わりができるようになり、保育の質を向上させることができますよ。また、療育の知識を持つことで、保護者へのアドバイスや支援の幅も広がり、信頼関係の構築にもつながります。さらに、療育のスキルを活かして発達支援や特別支援教育など、キャリアの選択肢を広げることも可能ですよ。療育について学ぶことは、保育士としての成長にもつながる重要な一歩となるでしょう。



