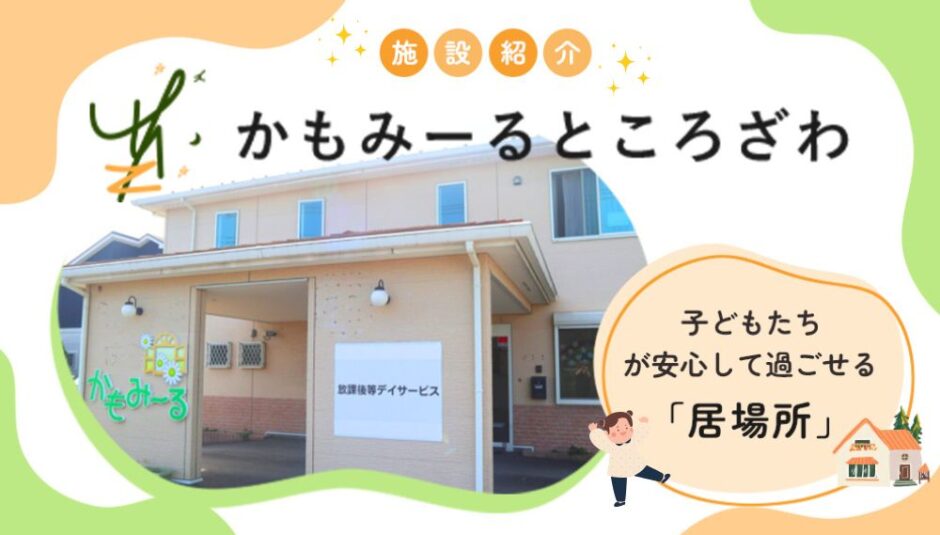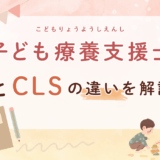開所から6年、子どもたちに寄り添う支援の場
2025年8月で開所から6年を迎えた放課後等デイサービスかもみーるところざわ。主に所沢特別支援学校に通う子どもたちが利用していて、現在は小学6年生が多めです。中学生は1名、高校生の利用は今のところいません。どの学年にも、おおよそ3人ほどが在籍しています。開所当初は、肢体不自由のあるお子さんを多く受け入れていましたが、最近では発達障害や自閉症スペクトラム、学習障害のある子どもたちが中心になっています。以前は男の子がほとんどでしたが、ここ数年で女の子の利用も少しずつ増えてきているとのこと。にぎやかで、和やかな雰囲気の中で、子どもたちはそれぞれのペースで過ごしています。かもみーるところざわという名前のとおり、カモミールのようにやさしく穏やかな雰囲気の中で、地域の中で大切な役割を果たしています。
施設立ち上げのきっかけ

代表理事の立石さんは、以前、児童発達支援管理責任者として、他の事業所で子どもたちの支援に関わっていました。当時勤めていた事業所が、やむを得ず閉所することになりました。それまで通っていた高校3年生の子たちが、卒業を目前にして通える施設がなくなってしまうという状況が生まれました。他の施設での受け入れ先も見つからず、このまま支援が途切れてしまうことに強い不安と危機感を抱きました。「それなら、自分で子どもたちの居場所をつくろう」と決意し、放課後等デイサービスかもみーるところざわを立ち上げました。一人ひとりが安心して過ごせる場を継続して提供すること。そんな思いが、この施設の出発点になっています。
支援を行ううえで大切にしていること
それぞれの特性に合わせたサポート

かもみーるところざわでは、子どもたちが毎日を安全に、そして安心して過ごせるよう、さまざまな工夫と配慮を行いながら支援しています。通ってくる子どもたちは、それぞれに発達障害や自閉スペクトラム症、学習障害などの特性があり、行動が予測しにくいことも少なくありません。遊びの中でテレビ台やロッカーなどに登ってしまう場面もありますが、思わぬケガを防ぐため、常に目配り・気配りを欠かさず過ごしています。机の角には緩衝材をつけるなど、環境面での安全対策も徹底しています。また、水分補給は子どもたち自身で管理するのが難しいため、決まった時間に全員で水分をとるようにするなど、健康面のサポートも大切にしています。玄関は、自動ドアを手動に変更し、つっかえ棒を設置。施設の目の前が道路という立地のため、万が一の飛び出しを防ぐための対策もしっかりと行っています。
見えない時間を見えるように
そして排泄についても個別に記録できるよう、トイレの前には子どもたちの名前と時計を表示した表を用意。誰が何時にトイレを利用したかを記録しておくことで、体調の変化や排泄のリズムを把握しやすくなり、保護者の方への情報共有にも繋がっています。そして、支援の中で特に大切にしているのが、見えない時間を見えるようにすること。子どもたちが施設でどのように過ごしているのかは、保護者にとって見えにくい時間です。そこで、かもみーるところざわでは日々の活動を写真や動画で記録し、保護者の方へ送ることで、安心していただけるよう努めています。お子さんの表情や日々の様子が伝わることで、家庭と施設とのつながりが深まり、信頼にもつながっていく。そうした思いを胸に、スタッフ一人ひとりが心を込めて日々の支援を行っています。
学校や家庭との連携について
学校へお迎えに行った際には、その日の子どもの様子について、担任の先生から直接申し送りを受けています。「今日はどんな様子だったか」「給食は食べられていたか」など、細かなことでも丁寧に確認し、施設での支援にしっかりと活かせるよう努めています。また、夕方にご家庭へ送り届ける際には、その日の様子や小さな変化も含めて、保護者の方にきちんとお伝えするよう心がけています。ご家庭と施設の間で情報が共有されていることは、お子さんにとっての安心や安定にもつながると考えています。さらに、万が一体調の変化や心身の不調が見られた場合にも対応できるよう、提携しているクリニックと連携し、必要に応じて速やかなサポートが行える体制を整えています。日々の小さなやりとりの積み重ねが、子どもたちの安心と成長につながっていくよう、スタッフ一同、丁寧な連携を大切にしています。
今後の展望について

かもみーるところざわが目指しているのは、子どもたちが将来障がい児から障がい者へと成長したときに、社会の中で自分らしく生活していける力を身につけられるように支援することです。そのために、今この時期から将来を見据えた訓練を意識的に取り入れています。たとえば、買い物体験を通してお金の使い方ややりとりを学んだり、食事会で人との関わりや公共のマナーに触れたりと、社会参加の“はじめの一歩”を積み重ねることを大切にしています。「いつか社会人になったとき、自分でできることが一つでも増えていてほしい」そんな願いを込めて、子どもたちの今と未来の両方に寄り添う支援を、これからも続けていきたいと考えています。