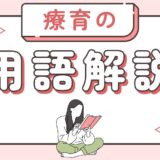皆さんは、ICFをご存知ですか?ICF(国際生活機能分類)は、介護や看護の現場で活用される国際的な分類方法です。従来のICIDHとは異なり、ICFは障害を持つ人の生活全体に着目し、支援の方向性を考える枠組みとして機能します。今回の記事では、ICFの目的や生活機能モデル、介護・看護現場での書き方例などを解説していきます。ICFを理解することで、より適切なケアや支援に活かすことができるでしょう。介護や看護に興味がある人は、ぜひ参考にしてみてくださいね。
ICF(国際生活機能分類)とは
介護や看護のアセスメントに役立つ国際的な分類方法
ICF(国際生活機能分類)は、世界保健機関(WHO)が2001年に発表した、介護や看護のアセスメントに役立つ国際的な分類方法です。ICFはInternational Classification of Functioning, Disability and Healthの略です。ICFは、従来の障害や病気に焦点を当てた分類とは異なります。生活機能に着目して、身体機能・構造、活動、参加や環境要因の4つの側面を統合的に評価しますよ。そのため、介護や看護の現場では利用者の健康状態をより詳細に把握し、適切な支援計画を立てる際に役立ちます。特に、リハビリテーションや介護サービスのアセスメントにおいてICFを活用することで、より個別性の高いケアを提供することが可能になります。
ICFの目的
生きることの全体像を示す共通言語の提供

ICFの具体的な目的は厚生労働省のホームページで以下のように記載されています。
・健康状況と健康関連状況とを表現するための共通言語を確立し,それによって,障害のある人々を含む,保健医療従事者,研究者,政策立案者,一般市民などのさまざまな利用者間のコミュニケーションを改善すること。
・各国,各種の専門保健分野,各種サービス,時期の違いを超えたデータの比較。
・健康情報システムに用いられる体系的コード化用分類リストの提供。
参考:https://www.mhlw.go.jp/houdou/2002/08/h0805-1.html
ICFは、これらの目的を通じて、より包括的な健康支援と障害理解を促進し、個人の生活の質の向上を目指す重要なツールとなっています。
ICFの生活機能モデル
心身機能・身体構造(生命レベル)

ICFにおける心身機能・身体構造とは、人の生命を維持するために必要な身体的および精神的な機能を指します。これには、筋力や関節の可動域、内臓や神経系の働きなどの身体構造と記憶力や感情のコントロール、知覚能力などの心身機能が含まれます。例えば、脳卒中後の片麻痺や認知症による記憶障害は、この領域に関わる問題ですよ。医療やリハビリテーションでは、これらの機能を改善または補助することを目的とし、適切な治療やトレーニングが行われます。
活動(生活レベル)
ICFにおける活動とは、日常生活の中で個人が行う行動や作業を指します。具体的には、食事や着替え、移動や会話など、生活を営むために必要な基本的な動作が含まれます。この活動レベルは、身体機能だけでなく環境や個人の意欲などにも影響を受けますよ。例えば、関節リウマチの患者が痛みのために服のボタンを留められない場合、心身機能の問題が活動の制限につながっていることになります。そのため、リハビリテーションや福祉用具の活用などにより、本人が自立して生活できるように支援することが重要です。
参加(人生レベル)

参加とは、社会や家庭、職場などで役割を果たし、他者と関わりながら生きることを指します。これは、単に身体機能や生活動作の能力だけでなく、個人がどれだけ社会的なつながりを持ち自分らしい人生を送れているかを評価するものです。例えば、車いすを使用している人が仕事を続けられたり、地域活動に参加できる環境が整っていれば、参加が確保されていると言えますよ。一方、身体的には移動できても、周囲の偏見やバリアフリーの不備によって外出が制限される場合は、参加の制限が生じていることになります。
健康状態
ICFにおける健康状態とは、病気や障害の有無だけでなく、個人の全体的な健康のバランスを指します。これは、心身機能・身体構造、活動、参加のすべてに影響を与え、逆にそれらの要素からも影響を受けるものです。例えば、高血圧という健康状態があっても、適切な治療と生活習慣の改善によって、日常生活や社会参加に大きな支障をきたさない場合もありますよ。一方で、同じ病気でも管理が不十分で合併症を引き起こせば、活動や参加が制限される可能性があります。
背景因子
環境因子
環境因子とは、個人の生活機能や健康に影響を与える、社会的・物理的な外部の要因を指します。これには、建物のバリアフリー化や交通機関の整備、福祉用具の利用、法律や政策などが含まれます。例えば、車いすを使用する人にとって、エレベーターの有無や段差の解消は移動のしやすさに直結しますよ。また、職場での合理的配慮が整っているかどうかも、働き続ける上で重要な要素となります。環境因子が整備されていれば、障害があってもスムーズに活動できる一方で、環境が整っていないと健常者と同じ能力を持っていても社会参加が困難になることがあります。
個人因子

個人因子とは、年齢や性別、生活習慣や心理的特性など個人の内面的な要素を指します。これらはICFの分類コードには含まれませんが、生活機能や健康状態に大きな影響を与える重要な要素とされています。例えば高齢者の場合、同じ身体機能の低下があっても健康への意識やリハビリへの意欲が高い人は自立した生活を維持しやすくなりますね。また、ポジティブな思考を持つ人は、病気や障害があっても積極的に社会参加しようとする傾向があります。一方で、ストレスや不安でネガティブな思考が強い場合、同じ病気であっても生活の質が低下しやすくなることもあります。ICFの視点では、こうした個人因子を考慮しながら、適切な支援やリハビリテーションの方法を検討することが重要とされていますよ。
ICFとICIDH(国際障害分類)の違い
障害の捉え方の違い
ICIDH(国際障害分類)では、障害を欠損、能力低下、社会的不利の3つの観点から分類し、主に個人の身体的・機能的な問題として捉えていました。例えば視覚障害がある人は、視力の欠損により就職の制限を受けるという社会的不利があるといったように、障害を個人の状態として評価するのが特徴です。一方、ICFでは、障害は個人の健康状態と環境要因との相互作用の結果として生じるものと考えられます。つまり、ICFでは障害を社会環境との関係の中で捉え、バリアフリーや支援の充実など社会全体の取り組みが重要であるとする考え方が採用されていますよ。このように、ICIDHが障害を個人の問題と捉えるのに対し、ICFでは社会的な側面も含めて包括的に障害を捉える点が大きな違いです。
健康と生活機能の包括的な視点の違い

ICIDHは、主に疾病や外傷による身体機能の損失や制約に着目し、医療的な視点から障害を評価していました。しかし、ICFでは障害を単なるできないこととしてではなく、どのような環境や支援があればできるのかという視点で捉えます。このため、ICFでは心身機能・身体構造、活動、参加だけでなく、それに影響を与える環境因子や個人因子も考慮して、より包括的な評価を行います。例えば、視覚障害がある人でも適切な補助具やテクノロジーの支援があれば、社会参加が容易になりますね。このように、ICFでは社会的要因や支援の可能性を重視する点が、ICIDHとの大きな違いであると言えます。ICFは現代のリハビリテーションや介護・福祉の分野で広く活用されていますよ。
ICFの評価点とコードの見方
評価点
ICFでは、心身機能や活動、参加などの各項目に対してどの程度困難があるかを評価するために、0~4の数字で表される評価点を用います。この評価点は、以下のようになっています。
・1=軽度の困難
・2=中等度の困難
・3=重度の困難
・4=完全な困難
・8=詳細不明
・9=非該当
これにより、客観的かつ標準化された形で生活機能の状況を記録することができます。
ICFコード
ICFコードは、各項目に対応するアルファベットと数字の組み合わせで構成されており、以下の記号とそれに続く3〜4桁の番号で分類されています。
・s=身体構造
・d=活動と参加
・e=環境因子
例えば、d450=歩行、b280=痛みの感覚、などそれぞれの機能や活動に対して固有のコードが割り当てられています。これにより、利用者の生活機能を詳細かつ体系的に記録することが可能となり、多職種間での情報共有がスムーズになります。
介護や看護の現場におけるICFの書き方例
健康状態

ICFの健康状態では、対象者が現在抱えている病気や既往歴、ケガや体調の変化など医学的な情報を中心に記述します。具体的には以下の通りです。
・高血圧および糖尿病の既往歴があり、服薬中
・関節リウマチにより朝方に関節のこわばりが見られる
診断名だけでなく具体的な症状や経過も記録することで、支援やケアの方向性が明確になります。医療情報を簡潔に、かつ現場で活用しやすい形で記載することがポイントです。
心身機能・身体構造
心身機能・身体構造の項目では、対象者の身体的機能や精神的機能、身体構造の状態についてを評価して記載します。例としては以下の通りです。
・皮膚の状態は良好
・精神的には落ち着いて穏やかに過ごしている
【マイナス面】
・右片麻痺があり、握力の低下が見られる
・構音障害により発語が不明瞭
心身機能は、日常生活動作や社会参加に大きな影響を及ぼすため、細やかな観察が重要です。変化が生じやすい部分でもあるため、定期的な評価と更新も必要ですよ。
活動

活動は、ADL(日常生活動作)に関する能力や実際の状況を具体的に記載します。例としては以下の通りです。
・食事は箸を使用し、自力で普通食を摂取できる
・排泄は完全に自立している
【マイナス面】
・入浴時の衣類の脱着に一部介助が必要
・調理は行っていない
・屋内移動は杖で自立、屋外は車椅子が必要
個々の活動の得意・不得意を把握することで、自立支援や介助内容の調整をする際に役立ちます。
参加
参加では、家庭内や地域社会でどのような役割を担っているか、また人との関わりがどの程度あるかを評価して記録します。具体例は以下の通りです。
・家族が面会に来てもあまり会話をしない
・日中はベッド上でテレビを見て過ごす時間が長い
参加状況は生活の質(QOL)にも大きく関係するため、精神的・社会的側面にも目を向けることが重要です。孤立を防ぐための支援の手がかりにもなりますよ。
環境因子
環境因子では、物的環境や人的環境、制度的環境の3つの観点から対象者の生活に影響する要素を記載します。例としては以下の通りです。
・人的環境:近隣に家族が住んでおり、通院時の付き添いが可能
・制度的環境:介護認定を受け、訪問介護を週3回利用中
こうした要因は本人の活動や参加に大きな影響を与えるため、正確な把握と評価が必要です。
まとめ
ICFの特徴を理解しよう
いかがでしたか。ICFは介護や看護のアセスメントに役立つ国際的な分類方法です。その特徴は、心身機能・身体構造、活動、参加といった生活の要素を統合して、背景因子である環境因子や個人因子との相互関係を考慮する点にあります。介護や看護の現場では、ICFの評価点やコードを活用し、利用者の状態を客観的に記録して分析をすることで、適切な支援計画を立てることができますよ。この記事を通してICFを理解し、現場で活かすうえでの参考になれば幸いです。