障害のある方を対象にした外出支援サービス、移動支援。「移動支援ってどんなサービス?」「行動援護とはどう違うのだろう?」と疑問に感じている方がいるかもしれません。また、「外出支援と言ってもどこまでが対象なの?」と不安に思っている方もいるでしょう。この記事では、移動支援と行動援護の違いやそれぞれのできることとできないこと、実際にサービスを利用する際の流れまで詳しくご紹介します。これからサービスの利用を検討している方や、障害者支援について興味のある方は、参考にしてみてくださいね。
移動支援とは?
障害がある方への外出支援サービス

移動支援とは、屋外での移動が困難な障害のある方を対象に、地方自治体が行う外出の支援サービスのことです。生活をするうえで必要不可欠な外出や、余暇活動といった社会参加のための外出を支援します。障害のある方は、日々の活動や外出を制限されてしまう場面が多くあるかもしれません。しかし、移動支援では移動介護従事者(ガイドヘルパー)が同行しサポートするため、一人で移動することが難しい方でも安心して外出することができるでしょう。地域での自立した生活や社会参加を実現することができそうですね。ただし、各自治体によってサービス内容や基準に違いがあるため、注意が必要です。
行動援護とは?
知的障害・精神障害がある方への外出支援サービス

行動援護とは、重度の知的障害・精神障害のある方を対象に、国が行う外出や行動の支援サービスのことです。移動時や外出先で必要な衣服の着脱・生活の介護、危険を回避するための援護などを行います。知的障害・精神障害のある方は個人ごとに行動の特性があり、外出先でのコミュニケーションが難しい場合や、強い不安と恐怖からパニック発作を起こしてしまう場合も。そのため、要望に応じた支援やより多くの対応が必要になります。また、国が行う事業のため、各自治体によるサービス内容や基準に違いがないことも特徴のひとつと言えるでしょう。
移動支援と行動援護の違いとは?
サービスの対象者
まず移動支援と行動援護の違いとして挙げられるのが、サービスを利用できる対象者の違いです。
| 対象者 | |
|---|---|
| 移動支援 | ・障害者等であって、市町村が外出時に移動の支援が必要と認めた者 |
| 行動援護 | ・障害者・障害児(重度の知的障害、精神障害) ・以下いずれにも該当 ①障害支援区分3以上 ②障害支援区分認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)に合計点数が10点以上である者 |
参考:厚生労働省
移動支援は、行動援護のように障害支援区分による対象者の限定がありません。そのため、身体障害者(全身性障害者)・知的障害者・精神障害者(発達障害者を含む)・政令で定める難病等により障害がある方も含まれる場合があるのが特徴です。
サービスの管轄
次に移動支援と行動援護の違いとして挙げられるのが、サービスを提供している管轄の違いです。
| 管轄(実施主体) | 制度・サービス | |
|---|---|---|
| 移動支援 | 地方自治体(市区町村) | 地方生活支援事業のサービス |
| 行動援護 | 国 | 障害福祉サービス(障害者総合支援法に基づく個別給付) |
行動援護は、国が定めたルールや規定に基づいて運用されています。それに対し移動支援は、各自治体が実施主体となり、地域の特性やサービスを利用する方の状況に応じて柔軟な形態で実施します。
サービスの内容
対象者や管轄が異なると、利用できるサービス内容にも違いがあります。
| 支援サービス内容 | 実施方法 | |
|---|---|---|
| 移動支援 | ・生活するうえで必要不可欠な外出 ・余暇活動や社会参加のための外出 など | 個別支援、グループ支援、車両移送 |
| 行動援護 | ・危険を回避するための援護 ・生活の介護 ・移動時や外出先で必要な衣服の着脱 ・排せつ及び食事の介護 など | 個別支援 |
移動支援の主なサービス内容は、外出や移動の支援です。また実施方法は、利用する方と地域の状況により個別支援・グループ支援などさまざまです。それに対し行動援護のサービス内容は、個別支援のみで、一人ひとりに合わせたより細かい援護・介護となっています。
利用時間数や費用
続いて、移動支援と行動援護の利用時間数や費用の違いを見ていきましょう。以下では、時間数別に見た自己負担費用の一例をご紹介します。
| 単価比較表 | 移動支援 A市(政令市) | 移動支援 B市(中枢市) | 移動支援 C市(一般市) | 行動援護 |
|---|---|---|---|---|
| 30分未満 | 255 | 220 | 230 | 258 |
| 30分以上1時間未満 | 402 | 380 | 400 | 407 |
| 1時間以上1時間30分未満 | 584 | 550 | 580 | 592 |
| 1時間30分以上2時間未満 | 666 | 628 | 655 | 741 |
| 2時間以上2時間30分未満 | 750 | 706 | 730 | 891 |
| 2時間30分以上3時間未満 | 833 | 784 | 805 | 1,040 |
| 3時間以上3時間30分未満 | 916 | 862 | 875 | 1,191 |
| 3時間30分以上4時間未満 | 999 | 940 | 945 | 1,340 |
参考:厚生労働省
移動支援や行動援護の利用費用は、サービスの総費用の1割が自己負担となります。1時間30分未満の短時間での利用だと、移動支援と行動援護の費用はそれほど差がありません。具体的な金額は地域ごとに異なるため、利用する際はお住まいの地域の制度を確認するとよいですね。
従業者の必要な資格
移動支援と行動援護の違いとして最後にご紹介するのは、従業者の必要な資格です。
| 必要な資格 | |
|---|---|
| 移動支援 | ・移動支援従事者養成研 修全身性課程 (全身性ガイドヘルパー) ・移動支援従事者養成研修 知的障害課程 (知的障害ガイドヘルパー) ・移動支援従事者養成研修 精神障害課程 (精神障害ガイドヘルパー) |
| 行動援護 | ・行動援護従事者養成研修または強度行動障害支援者養成研修(実践研修) ・知的障害や精神障害のある方への直接処遇経験1年以上 |
移動支援は、一般的に移動支援従業者養成研修の課程を修了することで業務に従事することができます。一方で行動援護は、行動援護従業者養成研修などの専門的な資格に加え、1年以上の実務経験が従事するうえでの必須条件となります。
移動支援でできることは?
生活するうえで必要不可欠な外出
移動支援でできることの1つは、生活するうえで必要不可欠な外出の支援です。具体的には、以下のような外出が挙げられます。
- 公的手続きや行政機関への外出(市役所・区役所・警察署・金融機関における手続き、公的サービスへの相談)
- 通院、保健所への外出
- 家族の学校行事への参加(入学式、卒業式、保護者懇親会など)
- 日用品の買い物(日常生活に必要な範囲)
- 理髪店、美容院への外出
- 住居に関わる外出(住居の取得、補修に関わる契約、不動産への相談など)
余暇活動や社会参加のための外出
移動支援でできることの2つ目は、余暇活動や社会参加のための外出支援です。具体的には、以下のような外出が挙げられます。
- 冠婚葬祭への参加、お見舞い
- 選挙への参加
- 自己啓発や教養を高めるための活動(講演会、文化教養講座への参加など)
- 生活の充実や質の向上のための外出(美術館、映画館、コンサート、動物園、外食、レジャーなど)
- 体力増強や健康増進のための外出(体育館、トレーニングジム、プールなど)
- ボランティア活動
個別支援型・グループ支援型などの柔軟な実施形態

また移動支援には、いくつかの柔軟な実施形態があることが特徴です。利用する方のニーズや地域の状況に応じて、各自治体が最適な形態を判断し実施します。では、柔軟な実施形態とは具体的にどのようなものでしょうか。1つ目は、個別支援型です。個別の支援が必要な場合には、障害のある方1人にヘルパーが1人付き添い、移動支援を行います。移動の際には、公共交通機関(バス・電車・タクシーなど)を原則として使用します。2つ目は、グループ支援型です。複数の障害のある方に対して、複数のヘルパーが同時に移動支援を行います。複数人が同じ目的地に移動する場合や、同じイベントに参加する場合などに利用することが最適ですね。また、地域によっては車両移送型も実施されています。公共交通機関の利用が困難な方を対象に、事業所の車両(福祉バスなど)で移動の支援を行います。
移動支援でできないことは?
政治活動や定期的・長期的な外出
移動支援は、際限なく利用できるわけではなく対象外となる外出・支援があります。以下のような外出・支援は、原則としてサービス内容には含まれないため、注意しましょう。
- 営業活動・経済活動に関わる外出(通勤など)
- 定期的かつ長期にわたる外出(通学、通所、通園など)
- 公共の秩序に欠ける場所への外出(ギャンブルなど)
- 政治活動・宗教活動に関わる外出
- 宿泊を伴う外出
- 利用する方のご家族など本人以外に対する支援
行動援護でできることは?
予防的対応

行動援護における主な支援には、予防的対応・制御的対応・身体介護的対応の3つがあります。まず予防的対応とは、知的障害や精神障害のある方による行動障害(自傷行為や他害行為、暴言など)が起きないように回避するための支援のことです。行動障害となる要因を取り除いたり、環境を調整したりすることで、発生しうる危険や行動障害を未然に防ぎます。具体的には、以下のような内容が挙げられます。
- コミュニケーション支援(ジェスチャーや筆談、コミュニケーションアプリなどで意思疎通を円滑にする)
- 環境調整(混雑した場所や大きな音のする場所などを避けた外出のルートや時間帯を工夫する)
- 事前の準備や予測(過去の事例から行動障害となる要因を分析し、具体的な方策を事前に講じておく)
- 専門的なアセスメントの実施(重度の行動障害がある方に対して、評価・分析を行い、個別の支援計画を作成する)
制御的対応
2つ目は、制御的対応です。制御的対応とは、利用者による行動障害によって本人や周囲の人に危険が生じる可能性がある場合に、緊急で行われる一時的な対応のことです。先述した予防的対応では解決できない、または間に合わないといったやむを得ない状況での最終手段として行います。あくまで支援の原則は予防的対応であることが重要な点ですね。制御的対応の具体例は、以下のような内容が挙げられます。
- 危険を回避するための介入や最小限の身体拘束
- 興奮状態やパニック状態にある利用者を安全な場所へ誘導し、落ち着きを取り戻す
身体介護的対応
3つ目は、心身介護的対応です。心身介護的対応とは、移動時や外出先での排せつ介助や食事介助のことです。行動障害により外出が困難な利用者に対し、一人ひとりの心身状態を理解したうえで、生活するための重要な支援を行います。
- 排せつ介助(便意を感じにくい、または認識できない利用者に対し、時間を決めてトイレに誘導し、排せつの介助を行う)
- 食事介助(外出先での食事の際に、食べこぼしを防いだり、食事の手順を示したりする)
- 更衣介助(ひとりで衣服を着替えるのが難しい方には着脱の手伝いを行う)
- 移動介助(転倒しないように側について歩いたり、車椅子での移動を支援したりする)
行動援護でできないことは?
政治活動や長期的・定期的な外出
行動援護も移動支援と同様で、際限なく利用できるわけではなく、対象外となる外出・支援があります。以下のような外出・支援は、原則としてサービス内容には含まれません。
- 営業活動・経済活動に関わる外出(通勤など)
- 定期的かつ長期にわたる外出(通学、通所、通園)
- 公共の秩序に欠ける場所への外出(ギャンブルなど)
- 政治活動・宗教活動に関わる外出
- 自宅内での介助・家事
- ヘルパー単独での外出や買い物
- 利用する方が自動車や自転車を運転する外出
- 利用する方のご家族など本人以外に対する支援
また、移動支援との併用はできないため、注意しましょう。
サービスを受けるまでの一般的な流れは?
お住まいの市区町村の福祉担当窓口へ申請する

まず、お住まいの地方自治体の障害福祉担当窓口(保健福祉センターなど)または指定特定相談支援事業者へ出向き、相談しましょう。対象者やサービス内容、基準は各自治体によって異なります。そのため、利用する方の状況やニーズを伝え、どのサービスを利用するのが最適か情報を得ることがポイントです。このとき、障害者手帳や医師の診断書などが必要になる場合があるため、同時に確認すると手続きがスムーズでしょう。どのサービスを受けるか決定したのち、申請手続きに進みます。
障害福祉サービス受給者証を受け取って契約する
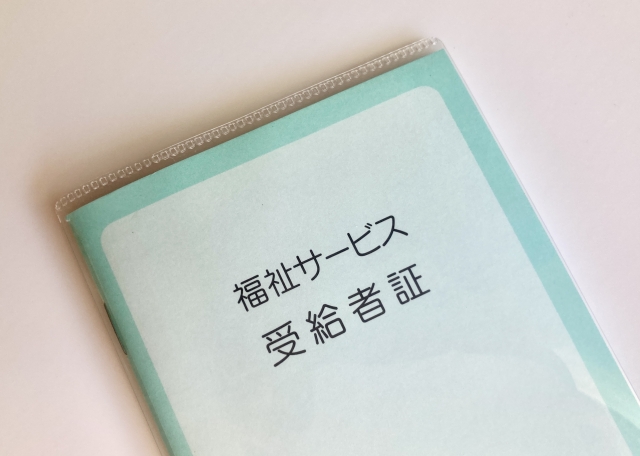
各自治体が申請書類や医師の意見書などの情報を総合的に審査します。サービスを受けることが適当だと判断されると、障害福祉サービス受給者証が発行されます。受給者証を受け取ったら、移動支援を行っているさまざまな事業所へ実際に足を運んでみるとよいでしょう。働いているスタッフの方の様子や事業所の雰囲気を見学し、利用する方に合うかどうか調べてみてくださいね。事業所を選択したら、受給者証を持参し事業所と契約を行います。もしサービス利用後に合わないと感じることがあった場合は、他の事業所に変更することも可能なため、その際は検討してみてもよいでしょう。
まとめ
移動支援と行動援護の違いを理解して利用しよう
この記事では、移動支援と行動援護の違いや、具体的なサービス内容をご紹介しました。移動支援においてのサービス内容は、各自治体が定める基準やルールによって千差万別です。お住まいの地域の自治体が公開しているホームページでより細かい基準やルールを事前に調べるのがよいでしょう。また行動援護においても、利用する方の行動特性をよく理解して適当なサービスを選択する必要があります。障害のある方ご自身や、支える周りの方が安心して日々を過ごすために、この記事が参考になれば幸いです。



